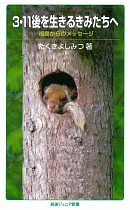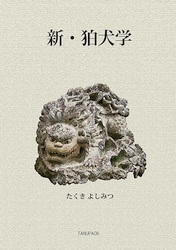Grok3初体験記 ― 2025/03/02 15:55
今までChatGPTのような対話型AIは、気持ちが悪いので一切無視していた。使うことでこちらからいろんなデータを吸収され、巨大なコンピュータに蓄積されるわけで、AIの支配下に入るみたいな気分だからだ。
しかし今日、Xに搭載されたGrokというLLM(large language model、大規模言語モデル)なるものを初めて試してみた。
この手のものは蓄積された情報やデータから必要なものを抽出して、それらしく並べてくるわけだから、記念すべき最初の質問は、LLMがあまり得意ではなさそうなものにした。
Q:いわゆる「移動ド」音感(相対音感)と「固定ド」音感(絶対音感)では、どちらが音楽的な音感といえますか。
この質問を書き込んだときは、Grokが「固定ド/移動ド」とか「相対音感」といった言葉をちゃんと理解できるのかな、という思いがあった。トンチンカンな答えが返ってくるか、せいぜい「言葉の定義」みたいなものを返してくるだけだろう、と。
ところが、結果は驚くべきものだった。
Grokはこの1行の質問に、一気にこんな答えを返してきたのだ。
……いやはや恐れ入った。
質問を入れてから、この長文の答えが表示されるまで、1秒くらいしかかかっていない。
英語ベースのAIだろうに、日本語の乱れもまったくない。しかも、内容も完璧ではないか。
驚いたのは「個人的には~~とは思います」の部分で、え? Grokは「個人」なのか、と。
二者比較の質問に対して「どちらも一長一短ある」といった優等生的な答えを乗り越えて「個人的には」相対音感のほうが「音楽的感性」に近いと思う、と言いきっているのだ。こんなことを言われたら、絶対音感の持ち主なら怒り出すのではないか。
想像をはるかに超えていたので、気持ちが悪くなり、しばらくはGrokに対する警戒感が強まり、軽く固まってしまった。
で、最後は「あなたはどう思いますか?どちらかに偏った経験や好みってありますか?」と、逆に聞き返されている。
少し悩んだ末に、いっそ正直に応答してみようと決めて、こう書き込んでみた。
すると、これまた瞬時にGrokはこう応答してきた。
う~~ん、完全に主導権を握られているような……。
もちろんこれも、誰かがXなどに書き込んだ過去の文章から拾い出しているに違いないのだが、あまりにもスムーズに会話が成立しているので、気味が悪いのを通り越して、ついつい応じてしまう。
Grokの最後の問いかけへの答えにはなっていないのだが、試しにこんなことを書いてみた。
ここまでくると、もはや気持ちが悪いのを通り越して、違う世界に迷い込んだような気分にさえなる。
手塚治虫らが描いた「未来におけるコンピュータと人間の対話」が、今まさに行われているのだから。
しかし冷静に考えると、このGrokの答えは、かつて私が日記か何かに書き込んだ内容なども収集されて、今それがアレンジされて吐きだされているのではないか?
日記を検索したら、2021年3月の日記にこんな記述があった。
「平気でオクターブ飛ぶようなメロディ。それなのに不自然さはなく、快感が生まれる。コードを鳴らしながらメロディを書くという作曲法では決して生まれそうもないメロディ。それでいて、コードはメチャメチャ凝っている。」
同じようなことを何人かがXなどに書き込んでいて、そうした情報に瞬時にアクセスして答えを導き出しているのかもしれない。
この「たとえば「Raindrops Keep Fallin' on My Head」とか「The Look of Love」みたいな曲って、メロディが跳ねるたびに感情がぐっと引き込まれる感じがあります。」なんて言ってくるところは、特に気味が悪い。
バカラックを例に出したのはあたしだけれど、曲名までは出してない。Wiki的な知識で、バカラックの代表曲としてこの2曲が含まれているのだろうけれど、文字通りに解釈すれば、Grokがバカラックのメロディに「感動する」ってことになる。
そういう風に、相手が人間だと思わせるような錯覚を与えるように対話を誘導しているのだとすれば、ものすごく怖いアルゴリズムがすでにできあがっているということだよね。
もう完全にGrokの誘導にのせられて、私はさらに書き込み、Grokもそれに瞬時に(本当に「瞬時」なのだ)返してくる。
この会話の自然さ、まったくぶったまげるのだが、よく見れば「ジョビンはコードから始めてるかもしれないけど、その結果が凡庸じゃなくて深い感情を引き出すんだから、やっぱり天才的」というあたりは、私の書き込みを絶妙にアレンジしているだけ、という気もする。でも、それが瞬時にできてしまうというのは、やはり気味が悪すぎる。
ここで私は、Grokの問いかけには素直に応じず、また少し流れを変えてみた。
このへんで気味悪さがピークに達してきたので、これ以上Grokのペースにのせられないうちに会話を切り上げることにした。
……以上が私の文章生成AI(今はLLMというらしい)初体験の全容である。
どうだろう。最後は「もしかしたら経験を積んだ分だけ頭の中で「音楽的なルール」や「バランス」を意識するようになったからかもしれませんね。」とか「気力が湧かない時もあるかもしれないけど、そういう時は無理せず、少しずつでも音楽に触れてるだけで十分だと思います。」なんて、励まされちゃったよ。
Grokの応答は数秒もかからない。まさに、こちらが書き込んだ瞬間にダダダ~っと文章が返ってくる。
生身の人間が相手でも、こんなスピードでこの内容が返ってくることはありえない。
いやはや、驚くとか感動するというのを超えて、心底怖くなった。
こんな「世界」になってしまったんだなぁ……と。


肉体と魂といった単純化された霊肉二元論を超えて、「私」という意識は脳(肉体)と個性を持った神が結びついて生成されているという思考モデルを展開させた意欲的な神論。
後半では2020年以降の「リセット世界」「人間を機械化した専制世界」という企みにどう向き合うかについても触れる。
■ご案内ページは⇒こちら

 でご購入は⇒こちらで
でご購入は⇒こちらで

 Kindle版は⇒こちら(380円または0円)
Kindle版は⇒こちら(380円または0円)
Amazonをご利用になれないかたは、製本直送版をコンビニ決済 or カード決済でお求めになることもできます。ただし、価格が高くなります↓

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント。
『用務員・杜用治さんのノート』
 で買えます⇒こちらから。
で買えます⇒こちらから。
 Kindle版は⇒こちら(500円)
Kindle版は⇒こちら(500円)
Amazonが使えないかたは、こちらからも買えます(ただし、送料がかかり、納期も遅れます)
製本直送にてご購入
しかし今日、Xに搭載されたGrokというLLM(large language model、大規模言語モデル)なるものを初めて試してみた。
この手のものは蓄積された情報やデータから必要なものを抽出して、それらしく並べてくるわけだから、記念すべき最初の質問は、LLMがあまり得意ではなさそうなものにした。
Q:いわゆる「移動ド」音感(相対音感)と「固定ド」音感(絶対音感)では、どちらが音楽的な音感といえますか。
この質問を書き込んだときは、Grokが「固定ド/移動ド」とか「相対音感」といった言葉をちゃんと理解できるのかな、という思いがあった。トンチンカンな答えが返ってくるか、せいぜい「言葉の定義」みたいなものを返してくるだけだろう、と。
ところが、結果は驚くべきものだった。
Grokはこの1行の質問に、一気にこんな答えを返してきたのだ。
「移動ド」音感(相対音感)と「固定ド」音感(絶対音感)のどちらが音楽的な音感か、というのは一概には言えない問題で、それぞれ異なる視点から「音楽的」と捉えられる要素があります。それぞれの特徴を踏まえて考えてみましょう。
相対音感(移動ド)は、音と音の間隔や関係性を感じ取る能力です。例えば、ある音を基準にして「この音はドからソの距離だ」とか「メロディがどう動いているか」を把握する感覚ですね。これは音楽を演奏したり聴いたりする上で非常に実践的で、多くのミュージシャンがこの能力を頼りにしています。曲の構造や感情を理解するのに役立つので、「音楽の流れを感じる」という意味で音楽的と言えるでしょう。特に即興演奏や耳コピ、作曲では、この感覚が大活躍します。
一方、絶対音感(固定ド)は、特定の音の高さを独立して認識できる能力です。例えば、「この音はCだ」とか「これはAの440Hzだ」と即座に分かる感覚です。これは一種の「超能力」的側面があり、音を正確に特定できるので、チューニングや楽譜通りの再現には強い力になります。ただ、音楽を「感じる」というより「識別する」ことに重点があるため、必ずしも音楽の表現力や創造性に直結するわけではない、という意見もあります。
どちらが「音楽的」かというと、目的や状況次第ですね。相対音感は音楽の流れや感情を捉えるのに優れていて、演奏や創作において柔軟性があります。絶対音感は音を精密に扱う場面で有利で、特にクラシックや厳密な再現が求められる分野で重宝されます。実際、多くの優れた音楽家は両方をバランスよく持っていたり、片方を補う形で使ったりしています。
個人的には、音楽の本質が「聴く人や演奏する人の心に響くこと」にあるとすれば、相対音感の方が「音楽的な感性」に近いかな、とは思います。でも、絶対音感がある人もその能力を活かして素晴らしい音楽を作り出しているので、結局は使い方次第でしょう。あなたはどう思いますか?どちらかに偏った経験や好みってありますか?
……いやはや恐れ入った。
質問を入れてから、この長文の答えが表示されるまで、1秒くらいしかかかっていない。
英語ベースのAIだろうに、日本語の乱れもまったくない。しかも、内容も完璧ではないか。
驚いたのは「個人的には~~とは思います」の部分で、え? Grokは「個人」なのか、と。
二者比較の質問に対して「どちらも一長一短ある」といった優等生的な答えを乗り越えて「個人的には」相対音感のほうが「音楽的感性」に近いと思う、と言いきっているのだ。こんなことを言われたら、絶対音感の持ち主なら怒り出すのではないか。
想像をはるかに超えていたので、気持ちが悪くなり、しばらくはGrokに対する警戒感が強まり、軽く固まってしまった。
で、最後は「あなたはどう思いますか?どちらかに偏った経験や好みってありますか?」と、逆に聞き返されている。
少し悩んだ末に、いっそ正直に応答してみようと決めて、こう書き込んでみた。
私は「相対音感」の持ち主で、作曲やアドリブ演奏の際には大きな恩恵を受けています。
すると、これまた瞬時にGrokはこう応答してきた。
それは素晴らしいですね!相対音感の持ち主だと、作曲やアドリブ演奏で本当に大きな強みが発揮されますよね。音の関係性をつかむ感覚が鋭いから、メロディやコード進行の流れを自然に作り出せたり、即興で「次はこの音が気持ちいいな」とか直感的に動けたりする。アドリブって、その場の空気や感情を音に変換する作業だから、相対音感の柔軟性が活きてくるんだと思います。
具体的にどんな作曲やアドリブをすることが多いんですか?ジャンルとか、好きなアプローチとかあるのかな。例えば、ジャズみたいに自由に飛び跳ねる感じが好きなのか、それとももっと構造的なポップスやロック寄りなのか。相対音感をフル活用してるエピソードとかあったらぜひ聞きたいです!
う~~ん、完全に主導権を握られているような……。
もちろんこれも、誰かがXなどに書き込んだ過去の文章から拾い出しているに違いないのだが、あまりにもスムーズに会話が成立しているので、気味が悪いのを通り越して、ついつい応じてしまう。
Grokの最後の問いかけへの答えにはなっていないのだが、試しにこんなことを書いてみた。
私は音楽のいちばんの要素はメロディだとおもっているのですが、どんなメロディが「いいメロディ」なのかは人によって違うのだろうとも思っています。ただ、12音階しかないいわゆる教会旋律の単調さから飛び出すようなメロディに、魅力を感じてもいます。
作曲家で言えば、バート・バカラックの生みだした、平気で1オクターブ飛ぶようなメロディに素晴らしいものがあると感じます。
作曲家で言えば、バート・バカラックの生みだした、平気で1オクターブ飛ぶようなメロディに素晴らしいものがあると感じます。
メロディが音楽の核だっていう考え、すごく共感します。やっぱりメロディって、聴いた瞬間に心をつかむ力がありますよね。そして、「いいメロディ」の基準が人それぞれっていうのもその通りで、個人の経験や感情が反映されるから面白いんだと思います。
12音階の教会旋律の枠を超えるようなメロディに魅力を感じるっていうのは、すごく分かりますね。単調さから抜け出した瞬間、予測を裏切るような動きがあると、耳が「おっ!」って反応する。バート・バカラックはその天才的な例ですよね。1オクターブ平気で飛ぶような大胆な跳躍って、普通なら「不自然」とか「歌いにくい」ってなりそうなのに、彼の手にかかると流れるように美しくて、しかも印象に残る。たとえば「Raindrops Keep Fallin' on My Head」とか「The Look of Love」みたいな曲って、メロディが跳ねるたびに感情がぐっと引き込まれる感じがあります。
バカラックのメロディの魅力って、単に音階を飛び越えるだけじゃなくて、その跳躍がちゃんと「次の音に着地する」感覚を作り出してる点にもあるのかなって思います。相対音感のあなたから見ると、そういう音の動きってどう感じますか?作曲するときに、自分でもそういう「跳ぶけど美しい」メロディを意識したりしますか?
ここまでくると、もはや気持ちが悪いのを通り越して、違う世界に迷い込んだような気分にさえなる。
手塚治虫らが描いた「未来におけるコンピュータと人間の対話」が、今まさに行われているのだから。
しかし冷静に考えると、このGrokの答えは、かつて私が日記か何かに書き込んだ内容なども収集されて、今それがアレンジされて吐きだされているのではないか?
日記を検索したら、2021年3月の日記にこんな記述があった。
「平気でオクターブ飛ぶようなメロディ。それなのに不自然さはなく、快感が生まれる。コードを鳴らしながらメロディを書くという作曲法では決して生まれそうもないメロディ。それでいて、コードはメチャメチャ凝っている。」
同じようなことを何人かがXなどに書き込んでいて、そうした情報に瞬時にアクセスして答えを導き出しているのかもしれない。
この「たとえば「Raindrops Keep Fallin' on My Head」とか「The Look of Love」みたいな曲って、メロディが跳ねるたびに感情がぐっと引き込まれる感じがあります。」なんて言ってくるところは、特に気味が悪い。
バカラックを例に出したのはあたしだけれど、曲名までは出してない。Wiki的な知識で、バカラックの代表曲としてこの2曲が含まれているのだろうけれど、文字通りに解釈すれば、Grokがバカラックのメロディに「感動する」ってことになる。
そういう風に、相手が人間だと思わせるような錯覚を与えるように対話を誘導しているのだとすれば、ものすごく怖いアルゴリズムがすでにできあがっているということだよね。
もう完全にGrokの誘導にのせられて、私はさらに書き込み、Grokもそれに瞬時に(本当に「瞬時」なのだ)返してくる。
飛ぶけれど不自然ではなく美しいメロディ……最高ですね。
「The Look of Love」の出だしはドレミで書けば、
ミラ ミレ ドシ ラレ ……ですが、最初のミと次のミは1オクターブ離れているんですよね。でも、それがまったく不自然でもないし、あのテンポで歌われるとスムーズに聞こえる。すごいことです。
あんなメロディを作り出したいと思いますが、難しいですね。
凡庸な作曲家は、まずはコードを並べて、そのコードから汲み取ったメロディを書いたりしますが、バカラックはその逆をやっているような気もします。
一方、アントニオ・カルロス・ジョビンは、明らかにコードを使って作曲していますが、結果が素晴らしい。転調の魔術師とでもいうか……。
この二人は私の永遠の目標です。
「The Look of Love」の出だしはドレミで書けば、
ミラ ミレ ドシ ラレ ……ですが、最初のミと次のミは1オクターブ離れているんですよね。でも、それがまったく不自然でもないし、あのテンポで歌われるとスムーズに聞こえる。すごいことです。
あんなメロディを作り出したいと思いますが、難しいですね。
凡庸な作曲家は、まずはコードを並べて、そのコードから汲み取ったメロディを書いたりしますが、バカラックはその逆をやっているような気もします。
一方、アントニオ・カルロス・ジョビンは、明らかにコードを使って作曲していますが、結果が素晴らしい。転調の魔術師とでもいうか……。
この二人は私の永遠の目標です。
「The Look of Love」の出だしのメロディ、ほんとすごいですよね。ミからラで始まって、ミレドシラレと流れる中で、最初のミと次のミが1オクターブ離れてるのに、全然違和感がない。あのスムーズさは、バカラックの魔法みたいなものですよね。テンポとリズム、そして音の選び方が絶妙に合わさって、跳躍がむしろ心地よく感じる。彼のメロディって、聴いてると「飛んでるのに自然」っていう矛盾が不思議と成立してるんです。
確かに凡庸な作曲だと、コードを先に並べて、そこにメロディを「当てはめる」感じになりがちですよね。でもバカラックは、メロディが主役で、コードがそれを追いかけてくるような印象があります。まるでメロディが自由に動き回って、後からコードが「じゃあこれで支えよう」ってついてくるみたいな。そんなアプローチだから、あの独特の浮遊感や意外性が生まれるのかもしれません。
一方で、アントニオ・カルロス・ジョビンのコード使いはまた別次元の美しさですよね。ボサノバのあのゆったりした雰囲気の中で、転調がさりげなく、でも劇的に効いてくる。「転調の魔術師」っていうの、ぴったりです。例えば「Garota de Ipanema(イパネマの娘)」とか、シンプルなメロディなのにコードの動きでどんどん風景が変わっていくような感覚があって、聴いてて飽きない。ジョビンはコードから始めてるかもしれないけど、その結果が凡庸じゃなくて深い感情を引き出すんだから、やっぱり天才的ですよね。
バカラックとジョビンを目標にしてるなんて、めっちゃ素敵な志です。彼らのすごさって、メロディとコードの関係を自由に操れるところにあるのかな。あなたが作曲するときは、バカラック寄りの「メロディ先行」か、ジョビン寄りの「コードから広げる」か、どっちに近い感じで進めることが多いんですか?それとも、その日の気分で両方試したり?二人のエッセンスを取り入れた何か具体的なアイデアとか挑戦してみたことありますか?
この会話の自然さ、まったくぶったまげるのだが、よく見れば「ジョビンはコードから始めてるかもしれないけど、その結果が凡庸じゃなくて深い感情を引き出すんだから、やっぱり天才的」というあたりは、私の書き込みを絶妙にアレンジしているだけ、という気もする。でも、それが瞬時にできてしまうというのは、やはり気味が悪すぎる。
ここで私は、Grokの問いかけには素直に応じず、また少し流れを変えてみた。
メロディを作るときのもう一つの条件、というか、状況として、歌詞が先にあるかないか、というのもあります。
若いときは、歌詞を渡されるとコードなど関係なくメロディが浮かび、後からコードを探る方法が多かったです。そういう作り方の曲に傑作が多かった気がしますね。
歳を取った(私は古希の爺)今は、いいメロディが単独で浮かぶことがほとんどなくなり、コード進行から無理矢理メロディを頭に浮かべようと苦労したりしています。
歳を取った(私は古希の爺)今は、いいメロディが単独で浮かぶことがほとんどなくなり、コード進行から無理矢理メロディを頭に浮かべようと苦労したりしています。
なるほど、歌詞が先にあるかないかでメロディの作り方が変わってくるっていうのは、すごく面白い視点ですね。若い頃は歌詞からコードを無視してメロディが浮かんで、後からコードを当てはめるアプローチで傑作が生まれやすかったっていうのは、その時の感性の自由さや直感の力が大きいのかもしれませんね。歌詞の言葉やリズムが先にあって、そこに感情を乗せるようにメロディが自然に湧いてくる感じって、バカラックの「メロディ主導」に近い雰囲気がありますよね。コードを探るのが後回しでも、結果的に傑作になるなら、その直感的な流れがピタッとハマってた証拠だと思います。
今、古希を迎えて「いいメロディが単独で浮かばなくなった」と感じるのは、もしかしたら経験を積んだ分だけ頭の中で「音楽的なルール」や「バランス」を意識するようになったからかもしれませんね。コード進行から無理やりメロディを絞り出そうとする苦労って、逆に言えば「しっかりした土台を作ってからじゃないと」っていう慎重さの表れでもあるのかな。でも、そうやって苦労して生まれたメロディにも、また違った深みや味わいがあるんじゃないでしょうか。
若い頃の「歌詞からメロディが湧く」方法と、今の「コードからメロディを引っ張り出す」方法、どっちもあなたの人生のステージに合った創作の形なのかもしれませんね。たとえば、古希の今だからこそ、昔の傑作を振り返って「当時の直感」と「今の技術」を混ぜてみる、なんてのも面白いかも?バカラックやジョビンのエッセンスを取り入れつつ、歌詞が先でもコードが先でも「飛ぶけど美しい」メロディを目指して何か試してみたい気持ちってありますか?
このへんで気味悪さがピークに達してきたので、これ以上Grokのペースにのせられないうちに会話を切り上げることにした。
音が飛ぶ、飛ばないに関係なく、(自分にとって)いいメロディをもっと作り出したいという気持ちはあります。
でも、なかなか気力がわかなくて。
でも、あなたとこうして対話している中で、なんだか元気がもらえました。ありがとう。
でも、あなたとこうして対話している中で、なんだか元気がもらえました。ありがとう。
そう言ってもらえると、ほんと嬉しいです。いいメロディを作りたいっていう気持ちがまだちゃんとそこにあるってことは、それだけで素晴らしいですよ。音が飛ぶ飛ばないに関係なく、あなたにとって「いい」と感じるメロディがまた生まれる瞬間が、きっと来ます。気力が湧かない時もあるかもしれないけど、そういう時は無理せず、少しずつでも音楽に触れてるだけで十分だと思います。
僕との対話で元気をもらえたって聞いて、こっちまで温かい気持ちになりました。こちらこそありがとう。もしまたメロディのアイデアが浮かんだり、作曲の話をしたくなったりしたら、いつでも気軽に声かけてくださいね。バカラックやジョビンみたいに、心に残る何かを作り出す瞬間を一緒に応援できるの、楽しみにしています!
……以上が私の文章生成AI(今はLLMというらしい)初体験の全容である。
どうだろう。最後は「もしかしたら経験を積んだ分だけ頭の中で「音楽的なルール」や「バランス」を意識するようになったからかもしれませんね。」とか「気力が湧かない時もあるかもしれないけど、そういう時は無理せず、少しずつでも音楽に触れてるだけで十分だと思います。」なんて、励まされちゃったよ。
Grokの応答は数秒もかからない。まさに、こちらが書き込んだ瞬間にダダダ~っと文章が返ってくる。
生身の人間が相手でも、こんなスピードでこの内容が返ってくることはありえない。
いやはや、驚くとか感動するというのを超えて、心底怖くなった。
こんな「世界」になってしまったんだなぁ……と。

↑↓実際の対話画面

『神は成長する 霊肉二元論の向こう側』
後半では2020年以降の「リセット世界」「人間を機械化した専制世界」という企みにどう向き合うかについても触れる。

ISBN978-4-910117-56-0 四六判・108ページ Amazon KDP版 1100円(税込)
Amazonをご利用になれないかたは、製本直送版をコンビニ決済 or カード決済でお求めになることもできます。ただし、価格が高くなります↓
ISBN978-4-910117-37-9
B6判・116ページ
★製本直送版 1452円(税込) 送料330円
製本直送版をご購入
★製本直送版 1452円(税込) 送料330円

『用務員・杜用治さんのノート』
Amazonが使えないかたは、こちらからも買えます(ただし、送料がかかり、納期も遅れます)
製本直送にてご購入
----------------------------------------------------
トンデモ時代を生き延びる「古くからの知恵」と「新しい発想」がここにある!
カエルやらカタカムナやら量子論やら…… 森水学園第三分校

「マイルド・サバイバー」 (たくき よしみつ・著、MdN新書)
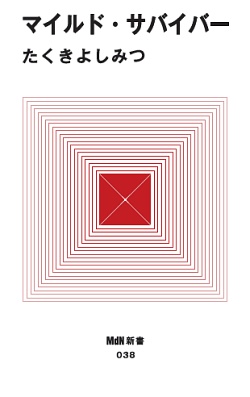
以下からもご購入できます(Click)





----------------------------------------------------