「フクシマ」と福島 ― 2016/03/20 22:04
「フクシマ」をカタカナでしか知らない人たちへのメッセージ
映画『Threshold: Whispers of Fukushima』の上映会がアメリカ・ミネソタ州の大学で開催されるにあたり、映画の中にも登場する僕に、何かメッセージを書いてほしいという依頼があった。少し前に日本語で書いたものを渡した。英訳されて使われるはずだが、そのときの元原稿をここにも残しておこうと思う。
2011年3月に福島県にある4基の原子力発電プラントが壊れて大量の放射性物質をばらまくという事件から5年が経ちました。
「フクシマ」はヒロシマ、ナガサキと並んで、世界的に有名な地名になりました。今、みなさんは「フクシマ」という地名に対してどんなイメージを持っているでしょうか。
悲劇の原発事故が起きた場所、放射性物質で汚染され、人が住めなくなった土地……おそらくそうした類のものだと思います。
それは基本的には間違っていませんが、現実のごくごく一部にすぎません。
せっかくの機会ですから、もう少しだけ想像を広げてみてください。そのためのヒントをいくつかあげてみます。
1)福島は広い
チェルノブイリのときもそうでしたが、壊れた原子炉から流れ出した放射性物質によって汚染された地域というのは、現場からの距離よりも、そのときの天候(風向き、雨や雪が降ったかどうか)によって決定づけられました。チェルノブイリのときに、遠く離れた北欧やドイツ南部などがかなり汚染されたように、「フクシマ」でも、汚染された場所は広範囲に点在しています。
福島県は日本の本州で2番目に広い県です。福島県内でも会津と呼ばれる西側のエリアはほとんど汚染されませんでしたし、一方では福島県以外のエリアでも深刻な汚染を受けた場所がいろいろあります。それらの地域の人たちは「福島県外」であるということで、十分な補償を受けることもできないという理不尽な状況も生まれました。
福島県内、とくに都市部では、多額の賠償金をもらった一部の避難者と、十分な賠償を受けていない県民との間で深刻な軋轢が生まれています。
汚染状況や賠償の格差などはとても複雑な問題であり、簡単に「フクシマ」という一言でくくれないということをまず理解してください。
2)とにかくこれからも生きていかなければならない
福島にはもう住めない、それなのに子供と一緒に住んでいる親は無責任だとか、危険なのに安全だと言って無理矢理住民を帰そうとしているといった批判が渦巻いています。これも、一部は正しいのですが、福島県内で今も暮らしている多くの人たちは、迷惑この上ないと感じています。
放射性物質がばらまかれたのですから、それ以前よりも危険が増したことは間違いありません。しかし、人が生きていく上で、危険や困難はたくさんあります。うっすら汚染された場所で生活を続けていく危険より、家族がバラバラになったり、収入が途絶えたり、生き甲斐をなくしたりすることによる危険、あるいは不幸になる度合や加速度のほうがはるかに大きいと判断することは間違いではありません。人はそれぞれの状況において、複雑な要素を比較した上で、取り得る最良の選択をしていくしかないのです。事情も条件もさまざまですから、一概に「それは間違っている」「正気じゃない」などと非難することはできません。
そう非難する人たちの中には、あのとき風向き次第では東京が壊滅していたかもしれないということを想像できず、無意識のうちに、自分たちは安全地帯にいるインテリ層だと勘違いをしている人も少なくありません。
自分たちがそうなっていたときにどんな選択肢が残されているか、まずはそこから考えてみるべきでしょう。
私は原発が爆発するシーンを見てすぐに逃げましたが、1か月後には自宅周辺の汚染状況を把握できたので、敢えて全村避難している村に戻って生活を再開しました。その後、やはり村を出て移住したのは、放射能汚染が理由ではなく、村の人々の心や生活環境がそれまでとは変わって(変えられて)しまい、私がこれ以上村に残っていても、地域のためにも自分のためにも、もう意味のあることができないだろうと判断したからです。その決断をするに至った背景はあまりにも複雑で、とても簡単には説明できません。
3)「フクシマ」は人間社会の構造的、精神的問題
壊れた原発内で放射線測定をする仕事を続けている20代の青年と話をする機会がありました。彼は使命感でその仕事をしているわけではなく、嫌だけれど他に仕事がないから辞められないだけだと言っていました。
いちばんの望みは、被曝線量が限度になると他の原発でも働けなくなるので、そうなる前に他の原発に異動できることだそうです。
いちばんショックだったのは「この村に生まれた以上、原発で働くしかない。そうした運命は変えようがない。仕方がない」という言葉でした。
まだ20代の若さでありながら、転職する気力もなければ、ましてや起業して自立するなどというのは「無理に決まっている」というのです。
おそらく、子供の頃は彼にも将来の夢があったでしょう。それがなぜそうなってしまったのか。大人になるにつれ「仕方がない」「これが運命だ」と諦めて、自分からは何もしなくなってしまう。人をそうさせてしまう風土や社会の空気、仕組み(システム)こそが、「フクシマ」が抱える最大の問題です。
「フクシマ」後初めての福島県知事選挙では、県民の半数以上が投票に行きませんでした。圧倒的多数で当選した県知事は、原発を誘致・推進してきた前知事の政策を継承すると言った元官僚で、与党ばかりか野党もみんな相乗りして支持していました。
地方が過疎化して、老人ばかりになる。残った人や自治体が苦し紛れに豊かな自然環境を金に換えてしまうために、森が消え、水や空気が汚染される。不合理なことに税金が使われ、その金に人びとが群がり、さらに問題が悪化する。……そうしたことは日本中、世界中で起きていることです。福島でも同じです。原発が壊れる前からありました。その背景にある問題は「フクシマ」を引き起こした問題と同じです。
そのことを深く考えないまま、核問題やエネルギー問題、経済問題を論じようとしても、正しい答えは得られないと思います。
「フクシマ」は決して「特別な問題」「特別な場所」ではありません。「不幸な事故」という認識も間違いです。政治や経済といった社会システムの欠陥、人の心の弱点が生み出したひとつの結果です。
この地球に生まれ、死んでいく私たちすべてが内にも外にも抱えている共通問題なのだ、ということを、私は「フクシマ」の現場にいたひとりとして、はっきりと証言いたします。
奇跡の「フクシマ」──「今」がある幸運はこうして生まれた
7つの「幸運」が重なったからこそ日本は救われた! 電子書籍『数字と確率で実感する「フクシマ」』のオンデマンド改訂版。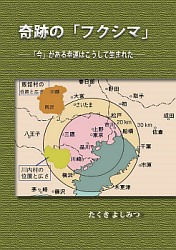 製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)
製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)新・マリアの父親
たくき よしみつ・著 第4回「小説すばる新人賞」受賞作『マリアの父親』の改訂版。
A5判・124ページ ★オンデマンド 980円(税別)
■ご案内ページは⇒こちら
■ご案内ページは⇒こちら
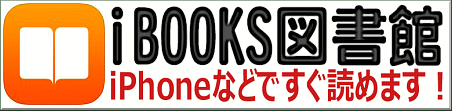
「フクシマ」を3.11に埋没させないために ― 2016/03/11 19:37
最大の危険要因は「人間」
関西電力広報担当職員 「いったんこれで今日終わりにします。今日ね、もう、並列(送電開始)なし。は~い。(横の誰かに向かって)タービンうまく並列できへんかった? (記者に向き直って)ちゃんとまた説明しますんで」
代表取材の記者(NHK?) 「はい。分かりました~ぁ」
広報担当 「いったんちょっと終わって、帰りましょうか」
取材記者 「はい」
2016年2月29日。
関西電力は、高浜原子力発電所4号機が送電を開始する瞬間をテレビでPRするために、中央制御室にテレビ代表取材のカメラを入れていた。
そのカメラの前で、職員が送電開始のスイッチを入れた途端にけたたましく警報音が鳴り響き、原子炉が緊急自動停止した。
↑上のやりとりは、同日夜の「報道ステーション」(テレビ朝日)で流れた映像の一部をそっくりそのまま文字起こししたものだ。
元北海道新聞社編集委員の上出義樹氏が関電に電話で確認したところ、代表取材で入っていたテレビ局はNHKだという。ということは、この間延びしたような返事をしているのはNHKの記者なのだろう。
このときの様子は近くの会場に集まっていた報道関係者たちに中継されていたが、そこにいた中日新聞の記者は以下のような記事を書いている。
「投入」。29日午後2時1分26秒、高浜原発4号機近くの関西電力原子力研修センター(福井県高浜町)で、報道関係者向けに中央制御室を映した中継映像から声が聞こえた。発送電を行うため、スイッチをひねって電気を流した合図。その直後から「ファー」という音が断続的に鳴り続けた。
センターで報道陣に作業内容の説明をしていた関電社員は当初、「異常がなくても鳴る警報もあります」と説明。画面の向こうの作業員らも慌てている様子はなかった。
しかし警報音は鳴りやまない。異変を感じたのは数分後。映像を前に、関電社員二人が耳打ちしながら指をさし始めた。その先には、上部の警報盤に赤く点滅するボタンがあった。
「トリップ(緊急停止)したようです」「制御棒が落ちて、原子炉が停止しました」と社員は動揺した様子で話した。トラブルの発生に、センター内の空気が一気に張り詰めた。間もなく関電は中継映像を遮断。詳しい説明を求める報道陣に対し、社員は「確認する」と、慌ただしくその場を離れた。
(2016年3月1日 中日新聞 米田怜央)
関西電力社員が「異常がなくても鳴る」と咄嗟にでまかせ説明をしたという部分で、すぐに思い浮かべたのは、2011年3月12日、福島第一原発1号機が爆発したときに、日本テレビのスタジオにいた東京工業大学原子炉工学研究所・有冨正憲教授とアナウンサーとのやりとりだ。
そのときの録画映像を見ながら、一字一句正確に文字起こししてみた↓
有冨教授 「緊急を要したんだろうと思いますが、爆破弁というものを使って、あたかも先ほどの絵じゃありませんが、全体にこう、なんといいますか、あの~、ちょっと、出るような形で……蒸気が、充満するような形で、出てきました」
アナウンサー 「あれは蒸気ですか?」
有冨 「蒸気だと思います。ちょうど爆破されたような形で、あの~、蒸気が……蒸気だと思いますが、出てきましたねえ」
アナ 「これ、あの、我々が見ると本当に心配するんですが、その爆破弁というものを使って蒸気を『出した』……という……」
有冨 「はい」
アナ 「意図的なものだと考えて……」
有冨 「はい。意図的なものだと思います」
このブラックコメディのようなシーンを覚えているだろうか?
よく分かってもいないことに対して平然と無茶苦茶な説明をする「専門家」たち。
そして、それを検証できず、ツッコミもせずにそのまま流してしまう、あるいは隠してしまうマスメディア。
同じことを5年経った今もやっている。何の反省もなく、当時よりも倫理観や責任感がゆるゆるに欠如した状態で。
「原発爆発の日」である3.12が5年目を迎えたのを機に、私たちはこれをしっかり思い起こし、反省しなければいけない。
巨大地震だの津波がまたやってくる可能性がどうのとかいっている前に、最大の危険要因は人間の愚かさだということを認識するべきだ。
チェルノブイリは天災が引き金ではなく、作業員のアホなミスやそれを起こさせた緩すぎる運営体制が原因だった。
今の日本を見ていると、チェルノブイリを起こした作業員たちより現場やトップが優れているだなんて、到底信じられない。
巨大地震や津波が襲ってこなくても、テロ攻撃されなくても、原発を動かしている、動かせている、それを許している、待ち望んでいる人たちがアホなのだから、「アホ」が原因の過酷事故は必ずまた起きる。
いや、アホが原因の事故というよりは、現代社会における原子力そのものが、アホと狂気のハイブリッドシステムというべきだ。
フェイスブックでこんなことを書いている人がいた。
普通のマンションでも40年で建て替えするのに、こんな50年前の時代遅れシステムを世界一安全という感覚自体が狂っている。政府や電力会社だけでなく、再稼働容認した自治体、住民は、万一の事故時には、被害補償放棄のみならず、他地区住民への賠償責任を負う、と法制化すべきだろう。
そう、まさにこの認識こそが重要なのだ。
「フクシマ」はいわば「裏切られた」「騙された」経験だから、原発立地の住民にも賠償するのは当然だと思うが、「フクシマ」を経験した今はもう違う。
「絶対安全」は嘘だった、ひどい運営状態だったことが分かっている。
今なお、「送電開始!」──警報音ファオンファオン……というお粗末を続けているこの国で、それでも原発政策を進めてほしいという人たちは、将来は自らが賠償責任を負う覚悟でそういいなさいね。
……と、これを書いている今は2016年3月11日。
テレビは「あれから5年」的な番組で一日中埋まるのかと思ったら、全然そうでもなくて、相変わらずご当地グルメだの野球賭博だのといった話題に時間を割いていたりする。まさに「5年間の劣化」だ。
せめて、「フクシマ」を地震や津波の被害と一緒くたに語るのはもうやめよう。
1F(いちえふ)が壊れたのは津波のせい「だけ」ではない。地震の揺れでパイプがあちこち寸断され、水が漏れたし、なによりも必要最低限の対策すら怠っていたための電源喪失だった。地震や津波は天災だが、「フクシマ」は完全な人災。 3.11というくくりで地震・津波被災と「フクシマ」問題を一緒くたに扱うことで、「フクシマ」問題の本質がどんどんごまかされてしまう。
よって、「フクシマ」がなぜ起きたのかを反省する日は3.12「原発爆発デー」とでもして、別問題として思いを新たにしたらどうだろう。
で、狂気の政策を続ける政治を容認している国民ひとりひとりも、程度の差こそあれ、このシステムを作り上げてしまった共犯者なのだという自覚を持つ。
まあ、実際には、我々はすでに「フクシマ」の後始末で、少なくとも十数兆円の「賠償」をしている。税金と電気料金という形で。
この「賠償」はこれからもずっと続けなければならない。
そのこともしっかり認識する日が、3.12。
……3.11とは違った恐怖と悲しみに包まれる……。
奇跡の「フクシマ」──「今」がある幸運はこうして生まれた
7つの「幸運」が重なったからこそ日本は救われた! 電子書籍『数字と確率で実感する「フクシマ」』のオンデマンド改訂版。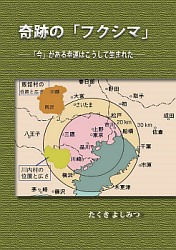 製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)
製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)新・マリアの父親
たくき よしみつ・著 第4回「小説すばる新人賞」受賞作『マリアの父親』の改訂版。
A5判・124ページ ★オンデマンド 980円(税別)
■ご案内ページは⇒こちら
■ご案内ページは⇒こちら
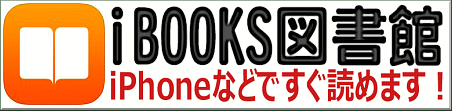
「いるだけ支援」のアニメを見て考えた ― 2016/02/17 22:54
「道を造りましたから通ってください」ではなく……
福島県が、『みらいへの手紙~この道の途中から~』というアニメーション動画を作って公開した。
一応全部見てみた。
8つ目の「いるだけなんだけど」がいちばん印象に残った。
(↑脚本・浅尾芳宣、演出・CGアニメ・佐藤貴雄)
このアニメーション制作にしても税金で作っているわけだが、いろんなプロジェクトが「支援」ていうことにしておかないと認められないようなところがある。
ちょっと調べてみると、この「いるだけ支援」というのは福島大学災害支援ボランティアセンターが企画したものらしい。
アニメでは、本当に「いるだけ」みたいな感じで、なんかいいなあ、と思ったのだが、実際にはどうなっているのか分からない。
まずは自分の名前を覚えてもらえるように大きく書かれた名前カードを首にかけて挨拶まわりを実施。後は普段通りに生活を送っていきます。
ここから大学に通い、アルバイトにも出かけていきます。
時間が空けば、庭先で日向ぼっこしながらおじいちゃんおばあちゃんと世間話にはなをさかせ、草が抜けないと聞けば代わりに草むしりに精を出す。頼まれたら快く引き受けます。
その姿は孫に近いものに見えました。
(Spotlight の記事より)
……なんていうリポートを読むと、なんだ、「いるだけ」じゃないじゃないの。相当大変なんじゃないの? と思ったりもする。
アニメから感じたことは、必要なのは「支援」じゃなくて「開放」だということ。
とりあえず「開放」して、後は放っておくだけでもいいんじゃないか、と。
仮設住宅に空き家がいっぱいあるから、とりあえず学生に「ここに入ってきてもいいよ」と「開放」する。
お金のない学生が、アパートより家賃が安いならいいかな……というノリでやって来る。
ノルマはなんにもない。
無理にイベントやったり、笑顔を作って話しかけたりする必要はない。普通に生活をするだけでいい。
積極的には何もしなくても、コミュニティに変化が生まれる(かもしれない)。
アニメの中で描かれているのはそんな情景だった。
そういうやつならいいんじゃないかなあ、と思ったのだが、実際にはお上からの許可を得るために、いろいろな名目やらなにやらを上奏しなければいけないのだろう。(結構大変だったと思う)
しかし、この「いるだけ」というフレーズは、とかく勘違いや余計なお節介ばかりになる公的「支援」策に一石を投じる可能性を秘めている気がする。
要するに、目的は村だの町だのじゃなくて、個人なのだ。
いろんな状況、立場、考え方の個人が、相対的に見て、より幸せになっていくようなシステム再構築。
映画『Threshold:Whispers of Fukushima』の中でマサイさんが言っていた言葉。
「ここに道を造りましたから通ってください、じゃなくて、一人二人とそこを通って行く人がいて、気づいたら自然に道ができていた──そういうのが好き」
……これ、すごく大切なことなんだよね。
奇跡の「フクシマ」──「今」がある幸運はこうして生まれた
7つの「幸運」が重なったからこそ日本は救われた! 電子書籍『数字と確率で実感する「フクシマ」』のオンデマンド改訂版。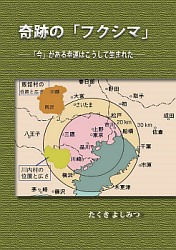 製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)
製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)新・マリアの父親
たくき よしみつ・著 第4回「小説すばる新人賞」受賞作『マリアの父親』の改訂版。
A5判・124ページ ★オンデマンド 980円(税別)
■ご案内ページは⇒こちら
■ご案内ページは⇒こちら
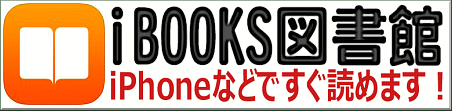
福島第一原発は東北有数の「電力消費地」 ― 2016/02/17 21:29
「凍土壁には関心ない」と言い放った田中委員長
1Fの「凍土壁」というの、まだやっていたんだなあ。
いくらなんでももうやめているんじゃないかと思っていたのだが、どれだけ税金や電気料金を無駄に使うのか……。
これに関してはどうも「税金を食い物にしたい」というよりも、今の日本、頭悪すぎる人が上にいることの悪夢、なんだろう。
原子力規制委員会の田中俊一委員長は13日、東京電力福島第1原発を視察した。汚染水の増加抑制策として1~4号機建屋周囲の土壌を凍らせ、地下水の流入を減らす凍土遮水壁も視察したが、「少しばかり水が入るのを減らしたからといって、汚染水問題は解決しない。あまり関心はない」と述べた。
田中委員長は「処理した水は海に捨てるという持続性のある形をつくらないと、廃炉は進まない」と指摘。汚染水の放射性物質を減らした上で海に放出するよう改めて求めた。
(時事ドットコム)
言葉を穏やかにしているが「関心ない」というのは「バカじゃないの?」と言っているに等しい。
まともな頭の人ならみんなそう思う。
一体これにどれだけの金を使っているのか。
凍らせるのは電力で凍らせるわけだが、今、1Fの現場では一体どれだけの電力を使っているのか。
東電はそれを公表すべきだ。
「私たちは本来電気を作る施設である発電所の不始末を片づけるために、毎日○○の電力を使用しています。これは一般家庭の使用する電力○○戸分に相当します。その分の電気料金はみなさまからいただいている電気料金に上乗せさせていただいております」
……とね。
こういうことがあと何十年続くのか分からない。多分、何十年では済まないだろう。100年後も、1Fを完全に後始末できているとは到底思えない。
これから先、たとえ過酷事故が起きなかったとしても、原発を動かせば放射性廃物が出続けることに変わりはない。
そして、その処分方法を人類は未だに知らない。
奇跡の「フクシマ」──「今」がある幸運はこうして生まれた
7つの「幸運」が重なったからこそ日本は救われた! 電子書籍『数字と確率で実感する「フクシマ」』のオンデマンド改訂版。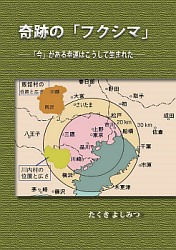 製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)
製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)新・マリアの父親
たくき よしみつ・著 第4回「小説すばる新人賞」受賞作『マリアの父親』の改訂版。
A5判・124ページ ★オンデマンド 980円(税別)
■ご案内ページは⇒こちら
■ご案内ページは⇒こちら
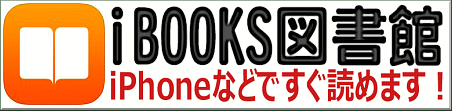
こうした形でも放射性物質は再拡散されている ― 2015/09/29 16:18
放射能汚染堆肥問題とは?
農林水産省のWEBサイトに「肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A」というページがある。東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴って、放射性物質が原子炉から大気中に放出されたため、家畜排せつ物、稲わら、落ち葉、樹皮等が放射性セシウムに汚染され、これらを原料として生産された堆肥が高濃度の放射性セシウムを含有する可能性があります。
普通肥料の中にも堆肥原料を混入したものがあり、肥料としてではなく土壌改良資材として農地土壌に施用されるものもあります。それらの中にも高濃度の放射性セシウムを含有する可能性のあるものがあります。
もし、高濃度の放射性セシウムを含む堆肥等を農地土壌に施用すると、土壌中の放射性セシウム濃度が増加し、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が食品衛生法の基準値を超える可能性が増えます。
また、個々の農家ごとに放射性セシウム濃度が大きく異なる堆肥等を施用すれば、同一地域内に放射性セシウム濃度の大きく異なるほ場が存在することになり、地域を単位として実施している野菜等の出荷制限や作付け制限の前提が崩れかねません。
そこで、農地土壌の汚染の拡大を防ぎ、食品衛生法上問題のない農産物を生産するため、肥料・土壌改良資材・培土に基準をつくりました。
……という説明がある。
2011年7月、秋田県内のホームセンター コメリで販売されていた栃木県産の腐葉土から11000ベクレル/kgという高濃度の放射性セシウムが検出されるという事態が起きた。きっかけは一般消費者が、持っていた線量計を製品に近づけたところかなりの線量を示したので「これはおかしい」と県に通報したことだった。
報じたメディアは少なかったが、こうしたことは日本全国で起きていたと思われる。
福島やその周辺では除染バブル現象が起きていて、本来なら伐らないはずの森林が伐採され、大量の植物・木質原料が堆肥用に回されている。
そこで国は、「国内で生産・流通・施用される全ての肥料・土壌改良資材・培土」について、放射性セシウム400ベクレル/kg以下という暫定基準値を作り、それを超えるものは出荷してはいけないということを決めた。
上の農水省のWEBサイトでもその経緯などを説明しているわけだが、引っかかるのは、腐葉土や堆肥などの製品に含まれる放射性物質の濃度をチェックして「農地が 汚染されないようにしましょう」と言っているだけという点だ。
「農地が汚染されると、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が食品衛生法の基準値を超えるかもしれない」と。
400ベクレル/kgという暫定基準値は、その程度のセシウム含有量であれば、「たとえ同濃度の肥料等を40年程度施用し続けても、過去の農地土壌中の放射性セシウム濃度の範囲内である100ベクレル/kg(事故前の最大値140ベクレル/kgを切り下げた値)を超えることがないから」だと説明しているわけだ。
これがまさに「お役所仕事」だなあと思う。
放射性物質は「吸い込む」ことがいちばん危険だという認識
本当に怖いのはそんなことではない。
農産物へのセシウムの移行については、僕個人は、今はあまり心配していない。
食物に微量の放射性物質が含まれていても、多くはそのまま体外に出ていくし、それによる内部被曝があったとしても微々たるもので、気にしてもしょうがない。余計な不安を抱いてストレスを増やすほうがはるかに健康に悪いと思っている。
普通に店で売られているものは、普通に食べている。多少はセシウムが含まれているかもしれないが、気にしないように決めた。
もちろんこの考え方(気にしないようにする)を押しつけるつもりはないし、食の安全を守るため徹底的に食べ物をチェックすること自体は今後もずっと続けなければならない。一個人として、自分の健康を守るためにはこれ以上ストレスを増やしたくない、ということにすぎない。
一方、何度も書いてきたことだが、微量であっても、ホットパーティクルを鼻や口から吸い込んで、それが肺に付着するなどした場合の内部被曝は、長期間、ピンポイントで被曝する可能性があり、線量の数値では計れない怖さがある。しかもそれは食品のように検査することができない。それが原因で肺癌やら心筋梗塞やらを起こしたとしても、因果関係の証明などまったく不可能だし、ほとんどの人はそんなこと想像もしないまま死んでいくことになるだろう。
上の写真は街の中、住宅街や農地に隣接した土地に堆く野積みされたバーク堆肥の山だが、屋根があるわけでも壁があるわけでもなく、風が吹けば堆肥は粉塵となって空中を浮遊する。
業者は原料も製品も250ベクレル/kg以下であることをチェックしていると言っているが、袋詰めされた製品のベクレル値が暫定基準値以下であっても、大量の堆肥が生活環境のど真ん中にこうした状態で積まれており、野天の場所に毎日ダンプトラックで運び込まれ、パワーショベルやベルトコンベアでかき回されているという「この状態」が恐ろしい。
仮にこの山積みされた堆肥が平均100ベクレル/kgのセシウム含有量だとしよう。規制基準は400ベクレル/kgだから、100ベクレルなら法的にはなんら規制を受けることなく「まったく安全な製品です」と言える。実際、そうだろう。
しかし、このバーク堆肥の山はどれだけの量があるのだろうか? 100ベクレル/kgだとして、1トンなら全部で10万ベクレルだ。10トンなら100万ベクレルという総量になる。それだけのものが一か所に山積みされ、なんの覆いも囲いもないところで、毎日パワーショベルやベルトコンベアでもうもうと粉塵を巻き上げながら作業されている。
我が家の周辺にはこうした業者の作業場が複数あるので、外から見られる範囲で見て回ったが、どこも同じで、屋根すらつけていない。完全に野地に山積み状態で作業している。
それほど利益率の高い事業ではなさそうだから、ドーム球場のような巨大な屋根付きの施設で作業をしろというのは現実には不可能だろう。それが分かっているから、国も行政もこうした問題は表面化させたくない。しかし、せめて周囲に人家や公共施設がまったくないような場所でやるべきではないのか。
堆肥工場による環境破壊は、悪臭、排水による河川の汚染、操業の騒音、出入りする大型トラックによる交通事故の危険性などが代表的なもので、実際、そうした被害にあっている住民からは苦情が絶えない。行政が立ち入り検査に入り、指導したりもしている。
しかし、目に見えない、臭わない、五感で感じられない放射性物質の空中浮遊(再拡散)という危険性については、調査も困難だし、住民も想像できないので気づかない。
先日の大雨で、大量の放射性ゴミのフレコンバッグなどが流出したことはニュースにもなった。そうなることは分かりきっていたのに、何を今さらと思う。
で、それもとんでもない話だが、雨で流れ出して川を下り、最後は海にまで運ばれていく放射性物質より、空中に漂うホットパーティクルを増やす行為のほうが恐ろしいのではないかと感じる。破れたフレコンバッグのように分かりやすくないから、見逃されがちだが……。
最近、我が家の線量計はときどき警告音を発する。一瞬だが、線量が上がって警告閾値を超えるのだ。すぐにまた下がるので、浮遊している放射性物質をたまたま捕捉して一時的に線量が上がったのだろうと解釈しているのだが、なぜそうなるのか、ずっと不思議だった。
2011年、2012年あたりより平均値は下がっているのに、瞬間的に上がる現象は今のほうが多いのだ。
福島からはるばる飛んでくるのだろうか? ありえなくはないが、イメージしにくい。そうであればなぜ今のほうが多いのか……と疑問に思っていたが、今では別の要因を疑っている。
堆肥工場の周辺を線量計を持って歩き回った結果、明らかに他の場所とは違う数値、挙動を示すことを確認したからだ(まさか、と思って、複数回、日を変えてやってみたが、同じ結果だった)。
もちろんこれは一つの論考に過ぎず、なんら証明ができない。地域においても極めてデリケートな問題なので、今までは書くことを封印し、自分の心の中に留めていた。
正直なところ、僕らはもうこうした問題にはほとほと疲れ果てている。触らずに忘れていたい。
生活環境は広く汚染されてしまったし、今もさまざまな形で破壊され続けている。
60代になった今、自分だけのことであれば、ローカルな問題に関与することで疲れるほうが、内部被曝の危険性よりずっと嫌なのだ。
かなりひどいことでもぐっと呑み込んでやり過ごそうとする。そうしていかないととても神経が持たない。
しかし、小さな子供や孫がいる人たちなどにとっては、見て見ぬ振りをしていい問題ではないはずだ。子供を守れるのは親だけなのだから。
また、これは本来ローカルな問題ではまったくなく、国がしっかり取り組むべき問題なので、やはり、一つの問題提起として書いておく。
堆肥製品に含まれるベクレル値ではなく、原材料の流通経路や製造過程の環境が問題なのだ、と。
すでに8月18日の日記にも書いたが、2012年8月の毎日新聞記事をもう一度引用しておく。
原発事故:福島の製材樹皮4万トン滞留 特措法の想定外
東京電力福島第1原発事故による放射性物質の影響で、製材時に生じる樹皮(バーク)が行き場を失い、福島県内の木材業者の敷地に計約4万トン山積みされて保管されていることが、県と県木材協同組合連合会(県木連、約220社)の調査でわかった。放射性物質を国が除去することなどを定めた放射性物質汚染対処特別措置法は、このような事態を想定しておらず、滞留バークは毎月数千トンずつ増え続けている。県木連は「業界の対応だけでは限界がある」として、東電に対策を求めている。
バークはスギやヒノキなどの表皮を3~5ミリはいだもの。家畜飼料や肥料などに使われるが、放射性セシウムの濃度が1キロ当たり400ベクレルを超えると出荷が禁じられ、滞留バークの多くがこの基準を上回っている。東電は汚染されたバークについて、保管場所設置費を損害賠償対象にしたが、処分や引き取りには応じていない。
県木連によると、バークはセシウム濃度の基準値を下回っても買い手がつかず、滞留量は増加の一途。焼却後の灰が同8000ベクレル以下の場合、国は一般廃棄物処分場での埋め立てを認めているが、焼却施設側が受け入れを拒否するケースが相次いでいる。
県木連の宗形芳明専務理事は「バークの体積を圧縮したり、敷地に余裕のある事業者が引き取るなどしてきたが限界だ」と話す。県木連は東電に▽石炭火力発電所での混焼▽仮置き場を東電所有地に設置▽木質バイオマス専用焼却施設の建設──などを要請している。東電広報部は「火力発電所での混焼は社内で検討中だ」としている。
バークの滞留は近隣県にも広がり、栃木県によると、3月末現在で計約3000トンが行き場がない状態だ。群馬県も「相当量が滞留している」という。
廃棄物の排出者責任に詳しい植田和弘・京都大大学院教授(環境経済学)は「将来の原子力事故も視野に入れ、国と東電は責任を持って法整備を含めた解決策を図るべきだ」と指摘している。【栗田慎一】
(毎日新聞 2012年08月03日)
原発爆発から4年半が経ち、溜まりに溜まった汚染バークのベクレル値も下がってきて、目下、どんどん堆肥へと姿を変えていることだろう。
堆肥というと園芸や農業用のものを想像する人が多いが、実際には土壌改良資材として道路工事などの公共事業用に多く出荷されている。先日の大雨であちこちの護岸や山腹が崩れたが、その補修工事にも大量に使われる。かくしてバーク堆肥は全国に運ばれていく。
国も、問題を伏せたまま、広く薄く、全国に拡散させてしまいたいに違いない。
なにしろ、水源地に放射能ゴミを持ち込むことを環境省がごり押しするような国なのだから。
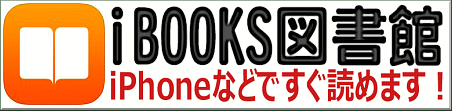
◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから
◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』
親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら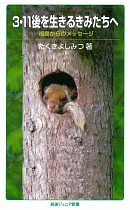
『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』
(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます
立ち読み版は⇒こちら
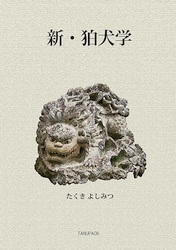
「狛犬本」の決定版!





