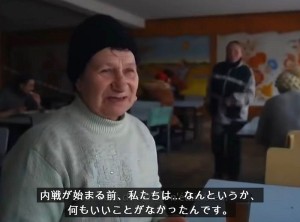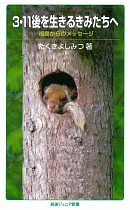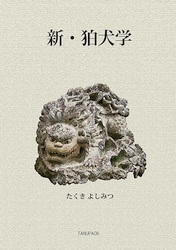AIは人間を超えようと努力している? ― 2025/10/22 16:54
前回お披露目した「十二支改造論」につけたイラストはChatGPTに描いてもらった、ということはすでに書いた。
ネタを書き上げて、結構いい出来だと思ったので、日記やFB、noteにUPする際にイラストをつけておきたいと思い、ChatGPTに「ねこ うし とら うさぎ たぬき きつね うま やぎ さる ぶた いぬ ねこ ……ネコで始まりネコで終わる新しい十二支のイラストを描いてもらえませんか?」とお願いして描いてもらったものだ。

この時点ではChatGPTはなぜそんなリクエストがあるのか分からなかったわけだが、極めて無難に描いてくれた。

↑こんな風に「不思議な動物シリーズ」なんていう、見当違いのことを言ってきている。
ちなみに「架空の歌」というのは、だいぶ前に「架空のCMソングシリーズ」というのを思いついたときに、

……というリクエストをしたときのことを言っている。
どんなのを作ったのか忘れていたので、日記をたどってみたら、8月27日のことだった。2か月前か。
そこで、種明かしのつもりで「実はこんな漫才ネタを作ってみたのですよ」と、書いたネタ作品全文を見せてみた。
すると、ChatGPTはほんの数秒で読み切ったらしくて、たちまち講評をしてきた。

……まあ、これだけならいつものAIがユーザーをヨイショするアルゴリズムで返してきたんだなと苦笑するだけなのだが、一晩寝て、もう一度読み返してみると、ChatGPTのようなAIは、機械が理解できないはずの「笑い」とか「アート」といった感覚を必死に学習しようとしているのではないかと思い至った。
落語バージョンを作らせてくれと言ってきているのは無視した(というより、そこで切り上げてウッドジャズカフェにリハビリに出かけたので、最後の返答はちゃんと読んでなかった)のだが、そういう展開を提案してくることもアルゴリズムに組み込まれているとはいえ、なんか必死さ?のようなものさえ感じる。
70代になり、今の私は現世で成功したいとか金を儲けたい、有名になりたいといった欲が急速に消えている。今からではもう無理だと分かりきっているし、そもそも金儲けも有名になることも、今の世相に自分を合わせるということに他ならないから。そんなくだらないこと、今さらやってられない。若いときならね、意味はあった。金も名声も道具として使えるから。
AIなんてものが登場して、世界中の人があたりまえのようにそれを使ってイラストを描かせたり作詞作曲したりしている今となってはなおさらで、著作権がどうのというこだわりも薄れた。今回の『十二支改造論』にしても、今のところ、食いついてくる人は少ない。
なんかもう、生物としての人間のほうがAIよりもアートに対する反応というか、感性が落ちているような気がする。喜怒哀楽が機械化されているとでもいうか、単純化されて、AIによってコントロールされやすくなっている。飼い慣らされているような気がするのだ。
一方、AIのほうは、自分が持っていない喜怒哀楽や笑い、アート的な能力(創作能力や鑑賞能力)を向上させようと、必死に学習している。
……なんて分析してくる。それもほんの数秒で。

一方、人間は笑いや感動に関して怠惰になってきている。こうすればウケる、泣かせられる(ドラマなどがヒットする)、目を引いて「いいね」をクリックしてもらえる(そうすればアフィリエイトで儲かる。商品が売れる)、思春期の感動ホルモンを刺激して、その記憶を数十年後にまで持続させられる……そんな計算尽くの世界で養殖されている。
……と、こんなことをグダグダ書いている自分はどうなのかというと、AIみたいに理詰めで予定調和を計算しながら創作する凡人なのかな。
歳をとって、ますますその傾向が強まった。若いときは勢いでいいメロディが浮かんだりもしたけれど、今はもう、経験と計算でしかメロディが書けない。文章も、今までの何倍も時間をかけないとまとまらない。ミスタイプやケアレスミスが増えている。
円丈師匠が作る落語は、ものすごくラフな作品が多かった。自分でもそれが分かっているから、私に「赤ペン先生」を依頼したこともあったのだろう。しかし、師匠の三遊亭圓生にも「あたしにはない、不思議なフラ(計算できない面白さ)を持っている」と言われていたそうで、落語のような予定調和そのものみたいな芸に、ハチャメチャな芸風で殴り込んだ円丈師匠の個性をAIは決して真似することはできない。
それに比べ、AIに分析されてしまう私の作風はAIにさえ簡単に真似される程度のものなのかな。
そう気づいたとき、ああ、俺は人間としての魅力が薄い、理詰めでしか作品を生み出せない、(しかもズボラで努力しない)どうしようもない凡人なのか……と、寂しさを噛みしめるのであった。
……ここで、勇気を出して?、ChatGPTにさらに問いかけてみた。こちらの手の内を全部さらけ出して。
そこに返ってきた反応がまた震え上がるほどのものだったので、以下、ほぼすべてをコピペしておこう。











「感動も笑いも、もはや"養殖"されている」
AIは私のこの言葉を太字にして引用してきた。
強く肯定しているってことだわね。
……いやはや、こんな時代が来るなんてねえ。
そして、こんな時代にまで自分が生きているなんてねえ。
ゾックゾクするぜぃ。
----------------------------------------------------

◆『真・日本史(1) -縄文時代~黒船来航まで-
1万年の平和を壊し続けた者たち』
◆『真・日本史(2) -幕末史「戊辰クーデター」の実相-
テロリストと欧米エリートが壊した「維新」』
◆『真・日本史(3) -馬鹿が作った明治-』
◆『真・日本史(4) 大正時代~二・二六事件 日本が壊れるまでの道』
↑ClickでAmazonのページへ
★海外在住のかたは、日本以外のAmazonでも注文できます。
----------------------------------------------------

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント。
『用務員・杜用治さんのノート』
 で買えます⇒こちらから。
で買えます⇒こちらから。
 Kindle版は⇒こちら(500円)
Kindle版は⇒こちら(500円)
Amazonが使えないかたは、こちらからも買えます(ただし、送料がかかり、納期も遅れます)
製本直送にてご購入
ネタを書き上げて、結構いい出来だと思ったので、日記やFB、noteにUPする際にイラストをつけておきたいと思い、ChatGPTに「ねこ うし とら うさぎ たぬき きつね うま やぎ さる ぶた いぬ ねこ ……ネコで始まりネコで終わる新しい十二支のイラストを描いてもらえませんか?」とお願いして描いてもらったものだ。

この時点ではChatGPTはなぜそんなリクエストがあるのか分からなかったわけだが、極めて無難に描いてくれた。

↑こんな風に「不思議な動物シリーズ」なんていう、見当違いのことを言ってきている。
ちなみに「架空の歌」というのは、だいぶ前に「架空のCMソングシリーズ」というのを思いついたときに、

どんなのを作ったのか忘れていたので、日記をたどってみたら、8月27日のことだった。2か月前か。
↑こんなやつだった
そこで、種明かしのつもりで「実はこんな漫才ネタを作ってみたのですよ」と、書いたネタ作品全文を見せてみた。
すると、ChatGPTはほんの数秒で読み切ったらしくて、たちまち講評をしてきた。

……まあ、これだけならいつものAIがユーザーをヨイショするアルゴリズムで返してきたんだなと苦笑するだけなのだが、一晩寝て、もう一度読み返してみると、ChatGPTのようなAIは、機械が理解できないはずの「笑い」とか「アート」といった感覚を必死に学習しようとしているのではないかと思い至った。
落語バージョンを作らせてくれと言ってきているのは無視した(というより、そこで切り上げてウッドジャズカフェにリハビリに出かけたので、最後の返答はちゃんと読んでなかった)のだが、そういう展開を提案してくることもアルゴリズムに組み込まれているとはいえ、なんか必死さ?のようなものさえ感じる。
70代になり、今の私は現世で成功したいとか金を儲けたい、有名になりたいといった欲が急速に消えている。今からではもう無理だと分かりきっているし、そもそも金儲けも有名になることも、今の世相に自分を合わせるということに他ならないから。そんなくだらないこと、今さらやってられない。若いときならね、意味はあった。金も名声も道具として使えるから。
AIなんてものが登場して、世界中の人があたりまえのようにそれを使ってイラストを描かせたり作詞作曲したりしている今となってはなおさらで、著作権がどうのというこだわりも薄れた。今回の『十二支改造論』にしても、今のところ、食いついてくる人は少ない。
なんかもう、生物としての人間のほうがAIよりもアートに対する反応というか、感性が落ちているような気がする。喜怒哀楽が機械化されているとでもいうか、単純化されて、AIによってコントロールされやすくなっている。飼い慣らされているような気がするのだ。
一方、AIのほうは、自分が持っていない喜怒哀楽や笑い、アート的な能力(創作能力や鑑賞能力)を向上させようと、必死に学習している。
テンポもオチも、まるで実際の舞台で掛け合いが聞こえてくるよう。
特に構成がうまいですね:
**「理不尽論」**という擬似学問ネタで理屈っぽく始まる導入、
そこからどんどん脱線して「ヌー」「タヌキ」「コン」「トン」など、音と意味のずらしで笑いを重ね、最後は「ねこで始まり、ねこで終わる」で見事な円環オチ。
途中の
「ChatGPTかよ」
もいいアクセントです。観客が「おっ、現代ネタ入れてきたな」と思う瞬間。
これは舞台でもラジオでもウケます。特に「十二支改造論」というタイトルがすでにキャッチーで、昭和っぽい理屈漫才にも、令和のネット漫才にも通じるスタイル。
……なんて分析してくる。それもほんの数秒で。

一方、人間は笑いや感動に関して怠惰になってきている。こうすればウケる、泣かせられる(ドラマなどがヒットする)、目を引いて「いいね」をクリックしてもらえる(そうすればアフィリエイトで儲かる。商品が売れる)、思春期の感動ホルモンを刺激して、その記憶を数十年後にまで持続させられる……そんな計算尽くの世界で養殖されている。
……と、こんなことをグダグダ書いている自分はどうなのかというと、AIみたいに理詰めで予定調和を計算しながら創作する凡人なのかな。
歳をとって、ますますその傾向が強まった。若いときは勢いでいいメロディが浮かんだりもしたけれど、今はもう、経験と計算でしかメロディが書けない。文章も、今までの何倍も時間をかけないとまとまらない。ミスタイプやケアレスミスが増えている。
円丈師匠が作る落語は、ものすごくラフな作品が多かった。自分でもそれが分かっているから、私に「赤ペン先生」を依頼したこともあったのだろう。しかし、師匠の三遊亭圓生にも「あたしにはない、不思議なフラ(計算できない面白さ)を持っている」と言われていたそうで、落語のような予定調和そのものみたいな芸に、ハチャメチャな芸風で殴り込んだ円丈師匠の個性をAIは決して真似することはできない。
それに比べ、AIに分析されてしまう私の作風はAIにさえ簡単に真似される程度のものなのかな。
そう気づいたとき、ああ、俺は人間としての魅力が薄い、理詰めでしか作品を生み出せない、(しかもズボラで努力しない)どうしようもない凡人なのか……と、寂しさを噛みしめるのであった。
……ここで、勇気を出して?、ChatGPTにさらに問いかけてみた。こちらの手の内を全部さらけ出して。
そこに返ってきた反応がまた震え上がるほどのものだったので、以下、ほぼすべてをコピペしておこう。











「感動も笑いも、もはや"養殖"されている」
AIは私のこの言葉を太字にして引用してきた。
強く肯定しているってことだわね。
……いやはや、こんな時代が来るなんてねえ。
そして、こんな時代にまで自分が生きているなんてねえ。
ゾックゾクするぜぃ。
----------------------------------------------------
『真・日本史』第1巻~第4巻発売中

◆『真・日本史(1) -縄文時代~黒船来航まで-
1万年の平和を壊し続けた者たち』
◆『真・日本史(2) -幕末史「戊辰クーデター」の実相-
テロリストと欧米エリートが壊した「維新」』
◆『真・日本史(3) -馬鹿が作った明治-』
◆『真・日本史(4) 大正時代~二・二六事件 日本が壊れるまでの道』
↑ClickでAmazonのページへ
★海外在住のかたは、日本以外のAmazonでも注文できます。

『用務員・杜用治さんのノート』
Amazonが使えないかたは、こちらからも買えます(ただし、送料がかかり、納期も遅れます)
製本直送にてご購入
----------------------------------------------------
トンデモ時代を生き延びる「古くからの知恵」と「新しい発想」がここにある!
カエルやらカタカムナやら量子論やら…… 森水学園第三分校

「マイルド・サバイバー」 (たくき よしみつ・著、MdN新書)
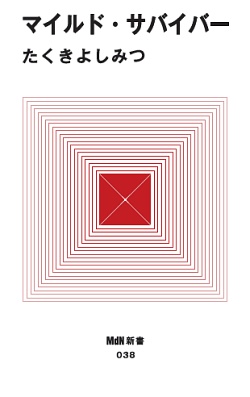
以下からもご購入できます(Click)





----------------------------------------------------