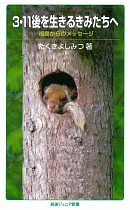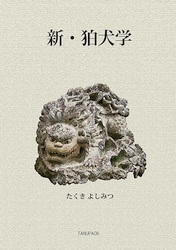もったいない学会とエントロピー学会 ― 2018/08/06 16:21
前出の「化石燃料枯渇後の再生可能エネルギー(再エネ)に依存する社会への移行は、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取)制度を用いた今すぐの移行ではありません 地球温暖化対策として、電力料金の値上げで国民に経済的な負担を強いる不条理なFIT制度を用いた今すぐの再エネの利用・拡大が、科学の常識を無視してやみくもに進められています」という文章は、「NPO法人 もったいない学会」というグループのサイトにあった。
もったいない学会の正式名称は「石油ピークを啓蒙し脱浪費社会をめざすもったいない学会」というらしい。
理事会名簿を見ると、
名誉会長:石井吉徳(東京大学名誉教授)
会長:大久保泰邦(産業技術総合研究所)
副会長:松島 潤(東京大学准教授)
……とあり、大学人や環境工学系企業の役員などで構成されているようだ。
なんだかエントロピー学会に似ているなあ、そういえばエントロピー学会は今でもあるのだろうかと検索したら、存在はしていた。室田武教授もまだ名を連ねていた。
僕の人生にいちばん影響を与えた本は、『資源物理学入門』(槌田敦、NHKブックス)と『エネルギーとエントロピーの経済学』(室田武、東洋経済新報社)だというのは、何度か書いているのだが、エントロピー環境論を知る前と後とでは、本当に人生観が変わった。
『マリアの父親』が「小説すばる新人賞」を受賞し、出版されたときは、まっ先にお二人に謹呈本を送った。するとすぐにお二人ともていねいな読後感想を書き送ってくださった。以後、今でも年賀状のやりとりは続いている。




上記登場する人たち(経産省グループの頭のいい人たちや「もったいない学会」に参加しているような学者やインテリ層)は、エントロピー環境論は理解しているだろう。その上で、合理性を無視して保身・出世のために事実を歪めて動く人たちと、真面目に真実を訴え続ける人たちがいるわけだ。
ほとんどの人たちはこの、生きていく上で最も根源的な「リアル社会の摂理」ともいうべき仕組みを理解していないし、知る機会も与えられていない。
どんなに努力しても、社会一般レベルでの理解度は深まらないのではないか。
となると、世間に向けて「こうなんですよ」と理屈を説明するよりも、(菅直人のような)理解していない政治家を啓蒙するほうが、成果は上がるのかもしれない。ルールを作るのは政治家たちなのだから。
では、政治家を啓蒙することができる人たちとは誰か。
本来は官僚たちがその役割を担わなければいけないのだが、魂がない、保身スキルだけ長けていく官僚が出世する。やはりその方向でも期待はまったくできないということか。脱力。
「もったいない学会」という名称はとってもダサいが、おそらく「エントロピー」という言葉を出しただけで多くの人に敬遠されてしまう経験を重ねたための苦肉の策なのだろう。ジレンマはよく分かるが、そこまで想像すると、やはり脱力してしまう。
「分かっている人たち」が集まって、その中で「そうなんだよね~」とやりとりしていても、ほとんどの人たちは耳を傾けないどころか目も向けない、気づかない、存在すら知らない。テレビのワイドショーやニュース番組もどきで言っていること、新聞のそれらしい評論が世の中の事実だと思っている。
でもまあ、脱力しているだけでは、ここまで書いてきた意味もないので、この「もったいない学会」のサイトで見つけたいくつかの注目される内容を列挙しておきたい。
田村氏の視点で注目すべきは、ロボットやAIを否定せず、「ちゃんと使え」と提言していることだ。これにはまったく同意する。もったいない学会の正式名称は「石油ピークを啓蒙し脱浪費社会をめざすもったいない学会」というらしい。
理事会名簿を見ると、
名誉会長:石井吉徳(東京大学名誉教授)
会長:大久保泰邦(産業技術総合研究所)
副会長:松島 潤(東京大学准教授)
……とあり、大学人や環境工学系企業の役員などで構成されているようだ。
なんだかエントロピー学会に似ているなあ、そういえばエントロピー学会は今でもあるのだろうかと検索したら、存在はしていた。室田武教授もまだ名を連ねていた。
僕の人生にいちばん影響を与えた本は、『資源物理学入門』(槌田敦、NHKブックス)と『エネルギーとエントロピーの経済学』(室田武、東洋経済新報社)だというのは、何度か書いているのだが、エントロピー環境論を知る前と後とでは、本当に人生観が変わった。
『マリアの父親』が「小説すばる新人賞」を受賞し、出版されたときは、まっ先にお二人に謹呈本を送った。するとすぐにお二人ともていねいな読後感想を書き送ってくださった。以後、今でも年賀状のやりとりは続いている。


上記登場する人たち(経産省グループの頭のいい人たちや「もったいない学会」に参加しているような学者やインテリ層)は、エントロピー環境論は理解しているだろう。その上で、合理性を無視して保身・出世のために事実を歪めて動く人たちと、真面目に真実を訴え続ける人たちがいるわけだ。
ほとんどの人たちはこの、生きていく上で最も根源的な「リアル社会の摂理」ともいうべき仕組みを理解していないし、知る機会も与えられていない。
どんなに努力しても、社会一般レベルでの理解度は深まらないのではないか。
となると、世間に向けて「こうなんですよ」と理屈を説明するよりも、(菅直人のような)理解していない政治家を啓蒙するほうが、成果は上がるのかもしれない。ルールを作るのは政治家たちなのだから。
では、政治家を啓蒙することができる人たちとは誰か。
本来は官僚たちがその役割を担わなければいけないのだが、魂がない、保身スキルだけ長けていく官僚が出世する。やはりその方向でも期待はまったくできないということか。脱力。
「もったいない学会」という名称はとってもダサいが、おそらく「エントロピー」という言葉を出しただけで多くの人に敬遠されてしまう経験を重ねたための苦肉の策なのだろう。ジレンマはよく分かるが、そこまで想像すると、やはり脱力してしまう。
「分かっている人たち」が集まって、その中で「そうなんだよね~」とやりとりしていても、ほとんどの人たちは耳を傾けないどころか目も向けない、気づかない、存在すら知らない。テレビのワイドショーやニュース番組もどきで言っていること、新聞のそれらしい評論が世の中の事実だと思っている。
でもまあ、脱力しているだけでは、ここまで書いてきた意味もないので、この「もったいない学会」のサイトで見つけたいくつかの注目される内容を列挙しておきたい。
太陽光発電の優遇は根拠がない
再エネ発電設備の実用化での効用を比較するには、この設備容量に設備の種類別の稼働特性ともみなされる年間平均設備稼働率の値を乗じて与えられる発電量kWhの値の実測値が用いられなければなりません。再エネ電力の利用・拡大で、設備稼働率の値が70 % 程度とされている地熱発電や中小水力発電などに較べて、稼働率の値がその1/6 程度の太陽光発電の利用の効果が、発電量ではなく、発電設備容量の値で評価された上で、FIT制度での最も高い電力の買取価格を設けて、優先的に、その利用・拡大が図られていることは、FIT制度の適用で、政府が太陽光発電事業者を特別に優遇していると言わざるを得ません。まさに、この国のエネルギー政策の混迷を象徴的に表していると言ってよいでしょう。
(「化石燃料枯渇後の再生可能エネルギー(再エネ)に依存する社会への移行は~」久保田宏、平田賢太郎)
「水素社会」など到来しない
輸送機関のEV化は移動機関「オール電化」である。しかし、長距離輸送の航空機と船舶の電動化はあり得ない。陸上自動車の燃料も石油代替の電力、「EVカー」である。それは日本において、原発の再稼働と水素社会のキャンペーンになっている。EVカーのエネルギー経済性を検討するまでもない。水素社会プロジェクトでは、地方で生産の再生可能エネルギーで水素製造し、EVに供給する迂回利用が滑稽にも真面目に語られている。利欲に染まった日本の支配層の視野はどこまで狭窄なのだろうか。原発も水素も石油インフラ依存の燃料であり、「EVの時代」はそんなに遠くない時期、恐らく21世紀半ばまでに安い石油が大幅に減耗し、石油代替エネルギーの経済性が破綻して、石油文明の存続が立ち行かなくなるともに終焉しよう。
日本国民の生活と五穀豊穣の国土の再生は、「大都市集中から地方再分散」、「都市の地方支配から都市と地方の共栄」にガラッと変えることにある。そのためには、ロボット・AI、IOTの正しい活用、大量に産まれる「技術的失業者」の希望ある地方移住が必要である。
(「自動車EV化」は石油文明終焉の表れ 田村八洲夫)
単にノスタルジックな田園風景賛美や江戸時代浪漫吹聴では現代社会が抱える問題は解決しない。
台風の進路を正確に予想できるコンピュータがありながら、なぜ経済政策はマヌケでデタラメなものばかりになるのか? それはコンピュータを正しく使おうとしていないからだ。目的が「多くの人びとが無理なく平和、幸福に暮らせる社会の実現」ではなく、支配層の保身や私利私欲になっているからだ。コンピュータがこんな使われ方をするなら、AIが合理的にコントロールする社会のほうがよほどまともだろう。
まともな社会像かどうかを見抜く
さらに田村氏は、まっとうな社会論かを見極める判断基準は、……という大前提を提示した上で、よく見る「ポスト石油社会」像の弱点や矛盾点を次のように指摘している。(要約)
である。(当然、②が「まっとう」)
- ①石油代替エネルギーによって、現代社会のかたちを維持しようとする社会像か
- ②石油に替わるエネルギーの質に合わせて、文明のかたちが決まるとする社会像か
≪太陽エネルギー社会論≫
太陽光エネルギーで、自動車、業務・家庭、電力等で使われている石油量(石油使用量の67%)300万バーレル/日を代替しようとすると、7億kWの発電設備、5,000?のパネル面積が必要。太陽光発電設備の大工業的な製造、リサイクルには効率的な石油燃料が必須。太陽エネルギーは、地産地消型自然エネルギーと考えるべき。
≪水素社会論≫
水の電気分解によって得られる(「二次エネルギー」である)水素ガスを化石燃料代替エネルギーにしようとする発想が根本的に間違っている。水を電気分解する膨大な電力は、何から作るのか。現実性がまったくない。
≪低炭素社会論≫
「地球温暖化人為論=CO2排出削減論」は主として原子力発電の推進で今の石油文明を継続させようという論になりがち。原子力発電には化石燃料が必要不可欠なので矛盾している。(しかも原子力を利用した後にできる廃物処理が不可能なので論外)
≪循環型社会論≫
大量生産・大量消費・大量廃棄の浪費社会から脱却し、資源循環を効率的に行って3R社会に転換しようする論。3Rは、リデュース、リユース、リサイクルの順に重要だが、実際には、経済成長に貢献しうるとしてリサイクル産業が重視されすぎている。エントロピーの高い廃物や廃棄物を有用物に加工するために良質なエネルギーを多量に使うのはナンセンス。金属等の資源の浪費をある程度抑えられても、多くの場合、石油等の化石燃料は節減されない。エントロピー増大の法則(熱力学第二法則)を無視したリサイクル論はかえって資源浪費につながる。
≪持続可能社会論≫
石油に依存する二次エネルギーの利用や産業・交通に依存できなくなってからの社会は、自然が循環してくれるエネルギーを基盤にするしかない。いいかえれば、高エネルギー浪費型の現代社会から、もったいない精神による「低エネルギー文明」に移行するしかない。そのためには、利欲のために自然を支配する論理ではなく、自然の性質を学び、自然と共生する論理・心の持ち方に、戻ることが決定的に重要。
(「ポスト石油の文明社会論 現代石油文明の次はどんな文明か」 田村八洲夫)

上記内容のコラムの筆者・田村八洲夫氏が書いた本『石油文明はなぜ終わるか 低エネルギー社会への構造転換』。本日到着

↑エントロピー環境論を子どもから大人まで伝えたいという気持ちで書いた、これは私の「遺言」です