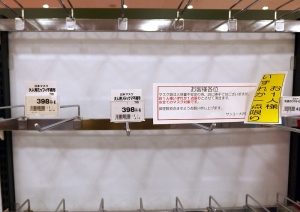医療現場に任せよ ― 2020/03/15 17:13
またまたCOVID-19の話か……とうんざりされそうだが、何年かして読み返すためにやっぱり記録しておこう。
原発爆発後のことも、私自身、あのときどう感じ、どう行動したのか、記憶が薄れているので、たまに当時の日記を自分で読み返して記憶を新たにしている。記録は生々しい内に残したほうがいい。
先日、都内の医師が匿名で投稿したこんな文章を読んでいた。
かいつまむと、
こうした状況というのは、SARSや2009年の新型インフルエンザのときに経験済みなはずなのに、日本ではその経験を生かして、次に新種の感染症が上陸したときの対応を整備していなかったので起きている。
やれたはずのシステム改革としては、
今日本がやっている大きな間違いは、本来研究機関である感染研が診療体制を仕切っていることだ。感染研がやるべきことは新種の感染症が出た場合、その正体に迫ってデータを積極的に公表することであり、一般診療体制に口を出すべきではない。
診療のための検査と研究のための検査は別物である。感染研はむしろ、発病者に関係なく、一定のエリアで無症状者を含めた定数サンプリングなどをして、新種のウイルスの感染率や発病率などを突きとめることだ。そのデータを医療現場に渡した後は、医療現場でどう対応するかは医療現場のプロに任せればいい。それなのに検査体制全体に口を出し、「重症化した人だけ検査」などということになっている。
ここが根本的な誤りなのに、未だに日本ではPCR検査を増やすべきか抑えるべきかなどという筋違いな議論を続けている。


原発爆発後のことも、私自身、あのときどう感じ、どう行動したのか、記憶が薄れているので、たまに当時の日記を自分で読み返して記憶を新たにしている。記録は生々しい内に残したほうがいい。
先日、都内の医師が匿名で投稿したこんな文章を読んでいた。
かいつまむと、
- 2月末、20代の生来健康な女性が発熱と咳で来院した。レントゲンを撮って肺炎ではないと診断して帰したが、その後も熱が下がらないため、3月7日、12日と3度来院。熱が10日ほど続いているということで、医師から帰国者・接触者センターに電話して、念のためPCR検査をしてほしいと伝えた。
- センターからの返事は「緊急性がないようであれば、今日は5時で業務が終わっている。明日になっても症状の改善がないなら、医師の方から保健所に連絡をして、指示を仰いでほしい。本人が保健所に電話をしても、検査はしてもらえないので」とのこと。
- ということは、肺炎等の病状としての「緊急性」がなければ、COVID-19の感染が疑われてもそのまま様子を見てしまってよいということなのか、と、驚いた。
- 「濃厚接触が疑われる場合であっても、本人から保健所に電話しても相手にされないのか」と確認すると、「濃厚接触者は国が全員を把握しているので患者さん側から申し出があることはあり得ない」との返答だった。だったら、なぜ濃厚接触が疑われる場合は電話相談をするように呼び掛けているのかまったく理解できない。
- 患者がかかりつけの医療機関を受診しても、肺炎が認められるまでは検査をしてもらえず、あちこちの医療機関を何か所も回ってようやく感染が発覚するという状況が蔓延していると聞いていたが、この対応では当然そうなると分かった。
- 我々クリニックの現場では、特殊な防護服もなく、マスクさえも手に入らないような状況で診療を続けている。しかも、コロナの感染者が受診したとなれば、風評被害も出るし、業務に支障も出る。こんな状況では診療を行いたくなくなる。
もし、重症ではないが、コロナかどうかわからない人を通常の日常生活にもどしてしまってさしつかえないのであれば、コロナ感染症を大げさにとりあえず通常の風邪として扱うべきです。そして重症化しない限り心配がないことを広く伝えていくべきです。
もし、コロナ感染症を特別な危険な感染症と本当に考えているのであれば、疑わしい患者さんをしっかり検査して、自宅隔離でも何でもよいので隔離措置をとるべきです。現在行われていることは、このどちらでもなくいたずらに不安と混乱を招き、医療現場を疲弊させる行為であると強く感じました。
(新型コロナウイルス、”持ちこたえている”という評価の中で現実に起きていること 医療ガバナンス学会メールマガジンVol.050)
こうした状況というのは、SARSや2009年の新型インフルエンザのときに経験済みなはずなのに、日本ではその経験を生かして、次に新種の感染症が上陸したときの対応を整備していなかったので起きている。
やれたはずのシステム改革としては、
- 高血圧や花粉症の薬をもらうためだけに病院を訪れるような無駄を減らせるよう、ネット診療システムを構築・拡充する
- 新種の感染症が広がったときに、一般のクリニックは「①発熱外来を別に作り、一般外来患者と診療動線を完全に分けて対応する」「②発熱患者専用病院に切り替わる」「③発熱患者は受け付けず、提携の①か②の病院に回ってもらう」の3通りに臨時編成する
- 感染の有無を素早く確認できるような検査システムをすぐに作れるようにしておく
- すぐに動ける専門家対策チームを平常時から組んでおく
今日本がやっている大きな間違いは、本来研究機関である感染研が診療体制を仕切っていることだ。感染研がやるべきことは新種の感染症が出た場合、その正体に迫ってデータを積極的に公表することであり、一般診療体制に口を出すべきではない。
診療のための検査と研究のための検査は別物である。感染研はむしろ、発病者に関係なく、一定のエリアで無症状者を含めた定数サンプリングなどをして、新種のウイルスの感染率や発病率などを突きとめることだ。そのデータを医療現場に渡した後は、医療現場でどう対応するかは医療現場のプロに任せればいい。それなのに検査体制全体に口を出し、「重症化した人だけ検査」などということになっている。
ここが根本的な誤りなのに、未だに日本ではPCR検査を増やすべきか抑えるべきかなどという筋違いな議論を続けている。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://gabasaku.asablo.jp/blog/2020/03/15/9224603/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから
◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』
親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら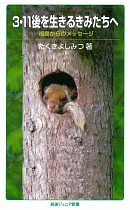
『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』
(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます
立ち読み版は⇒こちら
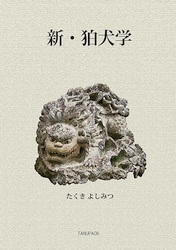
「狛犬本」の決定版!