福島第一原発で何が起きていたのか、今分かってきたこと ― 2011/04/06 16:08
2号機、3号機で何が起きたのか? 今、どうなっているのか?
ここ数日、気になる情報が矢継ぎ早に入ってきました。まずは、今中哲二氏(京都大学原子炉実験所助教)がリーダーとなって急遽編成された「飯舘村周辺放射能汚染調査チーム」が3月28日、29日に行った「飯舘村周辺において実施した放射線サーベイ活動の暫定報告」というもの。
http://p.tl/RN_n
↑PDFでここに発表されていますが、サーバーの能力が低いらしくて、常時重いので、一部内容をそのまま抜粋します。
3月28日と29日にかけて飯舘村周辺において実施した放射線サーベイ活動の暫定報告
飯舘村周辺放射能汚染調査チーム
調査メンバー:
今中哲二(代表) 京都大学原子炉実験所
遠藤暁 広島大学大学院工学研究科
静間清 広島大学大学院工学研究科
菅井益朗 國學院大學
小澤祥司 日本大学生物資源科学部
---------------------------------------------------
//3月15日午前の2号炉格納容器破壊または4号炉使用済み燃料プール火災にともない放射能大量放出があり、それが北西方向に流れて『高放射能汚染トレース』が形成されたものと推察される。
放射性ヨウ素がかなりの割合で存在することを考えると、06:10 に発生した2号炉格納容器破壊にともなう大量の放射能放出が北西方向へ向かったと考えるのが妥当であろう。
添付1のデータによると、飯舘村での放射線量率の最大値は、3月15日18:20 の 44.7μSv/h である。
右は、アメダス飯舘ポイントの当時の気象条件である。
3月15 日 06:10 の格納容器破壊で放出された放射能雲が約12 時間かけて飯舘村近辺に達し滞留・沈着したものと思われる。//
//図5に基づくと、3月15 日の沈着から90 日間の積算被曝量は、曲田で95mSv、村役場で30mSvと予想される。
この値は、あくまで牧草地などの土壌の上に常時滞在する場合であり、車中で2/3程度、木造でも家の中では1/2 程度、コンクリート製の建物中では1/10 に軽減されるものと考えられる。
なお、原子力安全員会の『原子力施設の防災対策について』に定める『屋内退避及び避難等に関する指標』においては、外部被曝による予測線量(放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置も講じなければ受ける線量)が10~50mSv のときは『自宅等の屋内へ退避すること』、50mSv 以上のときは『コンクリート建屋の屋内に退避するか、又は避難すること』と提案されている。飯舘村の放射能汚染状況が深刻なものであることは言をまたないものである。//
----------------------------------------------------
図や表は転載していませんが、要するにこれを読んで分かることは、
- これだけの高濃度汚染があることを国や関係機関は15日時点で分かっていたはずなのに、当該地区への情報伝達をしなかった
- (衝撃的映像として放送された)1号機、3号機の水素爆発よりも、むしろ映像としては伝わってこない2号機や4号機からの高濃度の放射性物質漏れが主要な原因と思われる。
- 飯舘村付近が突出して汚染されたのはそのときの天候条件による「たまたま」の結果である。つまり、他のどの地域も飯舘村並み、あるいはそれ以上に汚染された可能性がある。風が海側から吹いていた場合などは、首都圏で同様の汚染が起きたことも十分考えられる。飯舘村以外の場所の汚染が軽度だったのは、ものすごく運がよかっただけ。(実際、海洋上ではとてつもない汚染を受けたが、海水が薄めていることと、人がほとんどいないことで結果が出てこないだけ)
今中チームはどうやら、1号機や3号機の水素爆発よりも、2号機からの放射能漏れを重視しているようです。
2号機は外から見る限り、建屋があまり壊れていないので、1号、3号、4号機に比べればまともなのかと錯覚しがちですが、実は、3月15日午前6時10分に爆発を起こしています。東電は保安院に「この爆発により、サプレッション・チェンバー(圧力抑制室=上の図で、いちばん下に見えているドーナツ状部分)が損傷している恐れがある」と報告しています。
圧力抑制室は炉心に直結している部分で、原子炉本体と呼べる「圧力容器」の下部を構成しています。
タービン(原子炉外部にある蒸気発電機)が停止して原子炉から主蒸気をタービンに送ることができなくなったとき、蒸気をベント管等によりこの圧力抑制室に導いて冷却し、原子炉圧力容器内の圧力を低下させるための設備です。また、非常用炉心冷却設備(ECCS)の水源としても使用されます。
これが爆発により破壊された(要するに穴が空いて中の水が抜けた)というのです。
つまり、2号機ではこの時点で炉心内の放射性物質が直接環境中に吹き出したと考えられます。
1号機や3号機の爆発は、建屋が吹き飛び、めちゃめちゃになったものの、格納容器、そしてその中に収められている圧力容器は概ね無傷で残ったとされています(もちろんタービンと結んでいる配管などは大きく損傷しているでしょうから、そこからは漏れているはずですが)。
対して、2号機は炉心を構成する圧力容器の一部がすでに壊れているという恐ろしい事態になったわけですから、そこから環境中に出てしまった放射性物質の濃度は桁違いでしょう。
現地で、その後の冷却作業を2号機中心に切り替えたことも、事態の深刻さを裏付けています。
今中チームが考えたように、もし飯舘村の放射能汚染の主原因が2号機からの放射性物質拡散であったとすれば、2号機の圧力容器が壊れたままで、炉心に注入している水がだだ漏れである以上、これから先も、何が起きるか分からないということになります。
炉心の温度は確実に下がってきているので、再臨界などはまず起きないでしょうが、問題は、炉心部分と外界がつながってしまっている、遮る手段がない、ということなのです。
水を入れなければ燃料集合体が露出して炉内の温度が上昇し、そこから高濃度の放射性物質が空気中に出ていきます。それを防ぐためには水を入れ続けなければいけませんが、圧力容器が壊れて水が漏れるのですから、注入した水は循環することなくそのまま外に出て行きます。この水は炉心を通っている水ですから、とんでもない汚染水です。
その後の報道によれば、敷地内地下の配管系統やU字溝の類が古くてあちこち損傷していて、汚染水の流出経路もすぐには特定できないという信じがたい状況ですから、敷地内の土壌汚染はすでに致命的です。
燃料集合体が露出して炉心の放射性物質が空気中に出てしまう(風次第でどこに飛ぶか分からない)よりは、水浸しにして敷地の土壌と海を汚染させたほうがまだマシだという判断の下に、切ない作業が今も進んでいるのです。
4月6日になって、報道では「高濃度汚染水の漏れが止まった」と報じていますが、漏れが止まったということは、流入口が開いたままでの田圃の排水口を閉めたのと同じですから、これからは敷地内が田植え前の田圃状態になります。超高濃度汚染水でびたびたになった田圃で田植え作業ならぬ復旧作業を強いられるわけで、これはこれで想像を絶する図です。
ついでに言えば、15日の時点で、政府や東電、関係省庁などは、一気に周辺地域への汚染が進み、そのときの風向きと降雨により、高濃度汚染エリア(いわゆる「ホットスポット」)が飯舘村周辺にできたことを知っていました。
しかし、気象庁はだんまりを決め込み、日本気象学会理事長・新野宏は、気象学会会員である学者たちに「リサーチを勝手にするな。発表するな」と圧力をかけていたのです。
呆れたことに、この「お達し」は、これを書いている4月6日現在もまだ気象学会のWEBサイトに掲載されています。
消える前に当該部分を抜き出しておきます。
2011 年 3 月 18 日 日本気象学会会員各位
日本気象学会理事長 新野 宏
(~略)この地震に伴い福島第一原子力発電所の事故が発生し、放射性物質の拡散が懸念されています。大気拡散は、気象学・大気科学の1つの重要な研究課題であり、当学会にもこの課題に関する業務や研究をされている会員が多数所属されています。しかしながら、放射性物質の拡散は、防災対策と密接に関わる問題であり、適切な気象観測・予測データの使用はもとより、放射性物質特有の複雑な物理・化学過程、とりわけ拡散源の正確な情報を考慮しなければ信頼できる予測は容易ではありません。
今回の未曾有の原子力災害に関しては、政府の災害対策本部の指揮・命令のもと、国を挙げてその対策に当たっているところであり、当学会の気象学・大気科学の関係者が不確実性を伴う情報を提供、あるいは不用意に一般に伝わりかねない手段で交換することは、徒に国の防災対策に関する情報等を混乱させることになりかねません。放射線の影響予測については、国の原子力防災対策の中で、文部科学省等が信頼できる予測システムを整備しており、その予測に基づいて適切な防災情報が提供されることになっています。防災対策の基本は、信頼できる単一の情報を提供し、その情報に基づいて行動することです。会員の皆様はこの点を念頭において適切に対応されるようにお願いしたいと思います。
4月4日には、読売新聞が、気象庁が海外向けには放射性物質拡散予測データを渋々伝えているものの、国内に向けてはまったく発表していない事実を報じました。
国際原子力機関(IAEA)は、「国境を越える放射性物質汚染が心配されるときには、各国の気象機関が協力して拡散予測を行うこと」を要請しています。
これに従い、日本の気象庁も、東日本大震災当日の3月11日から毎日1~2回、放射性物質の拡散予測を計算していました。それを海外には伝えており、ドイツやノルウェーなどの気象機関はそのデータにさらに独自の分析を加えて拡散予想を公開していますが、事故の当事者国である日本国内では隠されていたのです。
■3号機の爆発は水素爆発だったのか?
もうひとつ気がかりなのは、3号機の爆発が1号機と同じ水素爆発だったのか、ということです。
私自身は今でもそう思っていますが、そうではないと見ている人もいるようです。
週刊現代4/16号に、福島第一原発の原子炉(米GE社のMark1)設計を担当したGE社のもと設計士・菊地洋一氏という人物のコメントが紹介されています。
「3号機だけが熱でグニャグニャに曲がっているでしょう。アメ状に折れ曲がっている。これは明らかに水素爆発ではありません。何らかの理由で鉄骨を溶かす800度以上の超高熱にさらされ、鉄骨の骨組みが溶けた。水素爆発ではここまでの事態にはならない。何かもっと重大な事態が起き、それがいまだに報告されていないか、誰も正確に事実を把握していないのでしょう」
3号機の爆発が1号機のときとはまったく違う規模だったことは、爆発映像を流したテレビでも言っていました。
煙の色も違うし、爆発の瞬間に炎が建屋を包んでいるし、煙も上方向に高く上った、という解説で、両方の爆発シーンを並べて比較した映像も紹介されました。
しかし、その後3号機も水素爆発だったと発表されてからは、誰もこのことには触れません。
本当に「何かもっと重大な事態が起き、それがいまだに報告されていないか、誰も正確に事実を把握していない」のであれば、その重大な事態とはなんなんでしょうか。
私自身は、今の情報だけであれば、3号機の爆発は水素爆発であり、1号機より大きな原子炉だったから溜まっていた水素も多く、爆発も大きかったのだろうと推測しています。
3号機の爆発が飯舘村のようなホットスポットを作りだした原因だったとすれば、逆に、これから先、爆発が起きなければ放射性物質の空中への大量飛散はないということになるので、むしろ安心できます。
このへんも、しっかり調査・分析して報告してほしいものです。
ところでこの菊池氏が同じ週刊現代の記事の中で、過去における驚くべき体験を証言しています。
1970年代末、彼がGEの設計士として福島第一原発に赴任していたとき、2号機の補修が必要になって作業を開始しようとしたところ、東京電力社内に原子炉工事をしたときの図面が残されていなかった、というのです。
福島第一原発の歴史を見ると、
1967年9月29日:1号機を着工する。
1968年(昭和43年)3月29日:国が2号機の原子炉設置を許可する。
1969年(昭和44年)4月4日:福島県と東京電力の間で「原子力発電所の安全確保に関する協定」が締結される。
7月1日:3号機の原子炉設置許可申請を提出する。
1970年(昭和45年)1月23日:国が3号機の原子炉設置を許可する。
7月4日:1号機において核燃料を初めて装荷する。
11月17日:1号機の試運転を開始する(翌年5月11日に記念式典を実施する)。
1971年(昭和46年)2月22日:5号機の原子炉設置許可申請を提出する。
3月26日:1号機の営業運転を開始する。
……となっています(Wikipedia参照)。
71年に営業運転を開始した原子炉の建設図面が、70年代末には東電社内に残っていなかった??
そんなバカな話があるでしょうか。
いくらなんでもこの記事は信用できないのではないかと私は思ったのですが、4月5日、高濃度汚染水が海に漏れだしていた件は、パイプやトンネルからではなく、その下の「砕石層」を通って流れ出していたという報道に接し、考えが変わりました。そこまでいい加減な工事をしていて、老朽化にも気づかなかったのであれば、最初から杜撰だった、気が緩んでいたということもありえるだろうと。
少し詳しく説明すれば、当初、汚染水が噴き出しているのを目視できた場所の上流には、電線などが通る管路や電源ケーブル用のトンネルなどがあって、汚染水はこれらを通ってきていることが分かりました。もちろんこれらは「水路」や「排水管」ではなく、ケーブル類をまとめて這わせたり、人間が点検しやすいように作っているトンネルですから、決して水が入ってはいけない通路です。
そこに高濃度汚染水が流れ込んできていること自体が大問題なのですが、その経路を遮断しても汚染水の海への流入は少しも止まりません。そこでさらに調べると、そうした通路の下に土台として埋めた砕石層(要するに土の中)を通っていることが分かったので、そこに直接止水剤を注入したというのです。
私は越後の家で「土壌浄化層」「土壌トレンチ」という土壌バクテリアを利用して排水を浄化するシステムを自分で作ったことがあるので、砕石層が水の通路になることは体感的にもすぐ分かるのですが、ここに通っているのは炉心を通過して高濃度に汚染された水なのです。これが、U字溝やパイプではなく、地面の下の土壌そのものに流れ出しているというのですから、もはや冗談にもなりません。
ここに止水剤を注入したとしても、今なお汚染水はだだ漏れ状態なのですから、敷地内はどんどん汚染水で水浸しになっているのです。
福島第一原発が今後どうなっていくのか、現時点では誰にも分かりません。
分かってきたのは、「想定外」の堕落、怠惰、無責任、無能力が、電力会社と政府、そしてアカデミズムの世界で構成される「原子力村」にて蓄積されていたことです。
今まで大きな事故が起きなかったことのほうが奇跡的と思わざるをえません。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://gabasaku.asablo.jp/blog/2011/04/06/5779719/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから
◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』
親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら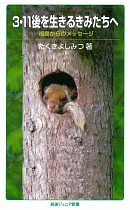
『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』
(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます
立ち読み版は⇒こちら
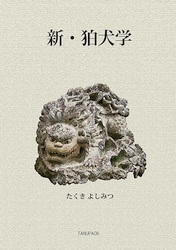
「狛犬本」の決定版!


